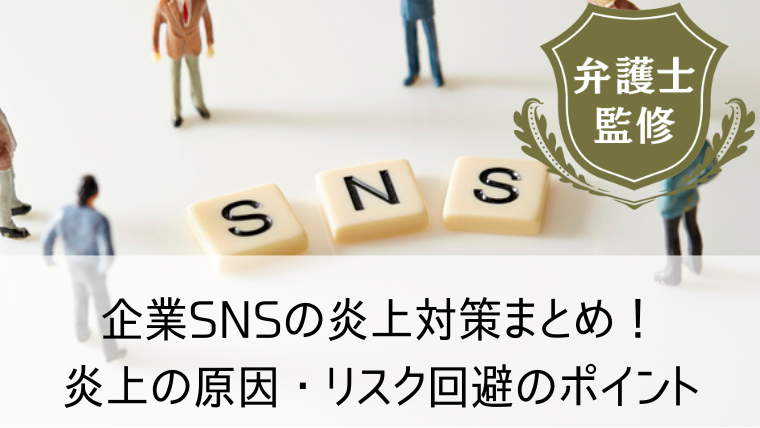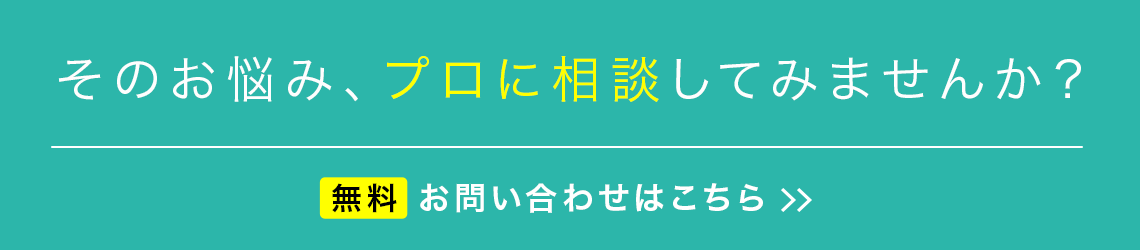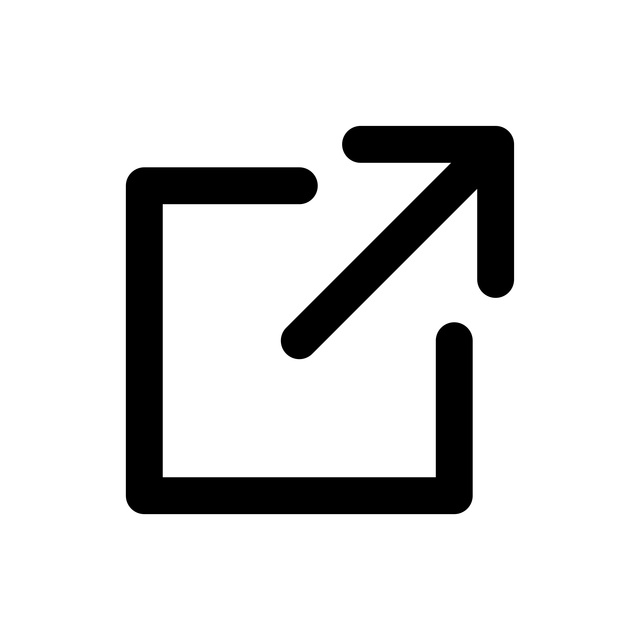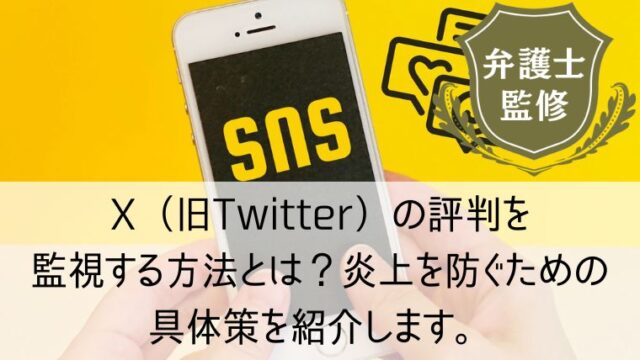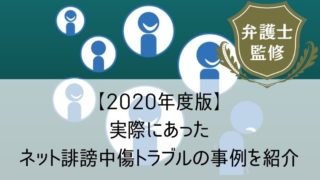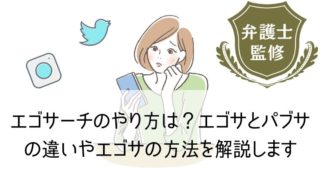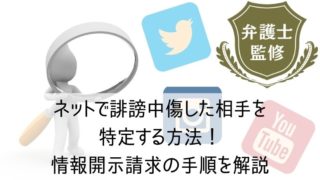SNSは企業にとって顧客との距離を縮め、ブランド価値を高める重要なツールです。
しかし一方で、投稿内容やユーザーとのやり取りが原因となり、「炎上」につながるリスクもあります。
SNSは投稿の拡散スピードが非常に早く、炎上が起これば企業イメージや売上の低下、法的トラブルなど深刻な事態を招く恐れがあるため、計画的な炎上対策を実施し、未然に防ぐことが重要です。
この記事では、企業SNSで炎上が起こる主な原因と、事前にできる炎上対策のポイントを分かりやすく解説します。
SNSの「炎上」とは
SNSにおける「炎上」とは、特定の投稿や発言に対して批判や非難が一気に集中し、コメントや拡散が止まらなくなる状態を指します。
スマートフォンとSNSが普及し始めた2011年を境に急速に増加しており、総務省の統計に掲載されているデータによると、2015年時点の炎上発生件数は1,002件、2006年41件の約24倍に拡大しました。
出典:総務省「令和元年版 情報通信白書」
近年はX (旧Twitter)やInstagram、YouTube、TikTokなどリアルタイム性の高いサービスの普及もあり、わずかな発言や不適切な対応が短時間で全国的に拡散する危険性が高まっています。
炎上が起こるメカニズムは、以下の通りです。
- SNS上で問題となる投稿や発言が拡散される
- 掲示板やまとめサイト、メディアでも取り上げられる
- SNS上でさらに話題となり、批判が一層広がる
総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、SNSや関連アプリを少なくとも月1回以上利用する国内ユーザーは2023年時点で1億580万人と推計され、若者に限らず幅広い年代に利用されるようになってきているのが現状です。
SNSの影響力が年々強まるなか、企業を守るための炎上対策は、現代のマーケティング活動に欠かせない取り組みとなっています。
企業の SNS が炎上する原因

続いては、企業SNSの炎上がどのようなきっかけで起こるのか、主な原因を紹介します。
不適切な投稿
SNSアカウントでの以下のような投稿は、不適切とみなされ炎上の火種になりやすい代表例です。
- 差別的な発言
- 社会的弱者やマイノリティに対する配慮を欠いた発言
- ルッキズムを助長する発言
- 他ユーザーやフォロワーへの威圧的な発言
SNSの炎上は、投稿者本人の意図に関わらず、受け手の印象で批判が拡大することが多いため、炎上対策を行ううえで最初に見直したいポイントといえます。
SNSを運用する際は、表現を慎重に確認したうえで、投稿前に社内チェックを行う体制を整えることが重要です。
バイトテロ
従業員が不適切な行動を個人アカウントに投稿し、そこから企業批判へと発展する「バイトテロ」も近年問題視されています。
厨房での悪ふざけや衛生管理を無視した行為などが動画として投稿されると、従業員個人への批判にとどまらず、企業全体の管理責任が問われます。
SNS利用ガイドラインの策定や研修、定期的な注意喚起など、バイトテロによる炎上を防ぐ対策も必要です。
誤った投稿(誤爆)
個人アカウント向けに作成した投稿を、誤って企業公式アカウントに投稿してしまう「誤爆」も炎上のきっかけとなります。
特に、スマートフォンで複数アカウントを管理している場合に起こりやすく、内容によっては企業の信頼を一瞬で失う可能性もあります。
企業SNS専用の端末を用意するなど、基本的な炎上対策が必要です。
ユーザーからのクレーム
炎上は公式アカウントの発言だけでなく、商品や広告に対するユーザーからの批判的な投稿がきっかけとなる場合もあります。
不適切な広告表現やサービスの不備が指摘され、口コミやリポストを通じて急速に拡散されるケースです。
SNSの運用だけに注意を払っても、商品企画や広報活動への配慮が欠ければ炎上は防げません。
広報や商品開発、カスタマーサポートが連携し、炎上対策を社内全体で共有することが重要です。
内部告発
従業員や関係者が、職場でのハラスメント、コンプライアンス違反、労働基準法違反などをSNSに投稿し、企業アカウントが炎上するケースも増えています。
かつてはメディアや週刊誌に持ち込まれていた内部告発が、今や誰でもワンクリックで発信可能になりました。
SNSでの炎上を防ぐには、社内に相談窓口を設置するなど、根本的な対策が必要です。
個人情報・機密情報の流出
個人情報や機密情報の漏洩は、企業への信頼を失墜させる重大なリスクの一つです。
システム障害や外部からの不正アクセスだけでなく、担当者のミスによる資料公開など、人的要因でも発生します。
事実がSNSに投稿されれば瞬時に広がり、顧客離れや取引停止など深刻な事態に陥るでしょう。
定期的なセキュリティ教育やアクセス権限の見直しなど、複合的な炎上対策が必要になります。
実際に起きた企業のSNS炎上事例5つ
SNSでの炎上は、業種や企業規模に関係なく、どの企業にも起こり得るリスクです。
公式アカウントの一投稿が大きな批判を呼び、不買運動や株価下落につながるケースも珍しくありません。
過去の事例を学ぶことは、効果的な炎上対策を考える上で非常に重要です。
ここでは、実際に発生した企業のSNS炎上事例を5つ紹介します。
1.東洋水産「赤いきつね」CM炎上(2025年)
2025年2月、東洋水産がX (旧Twitter)の公式アカウントで公開した「赤いきつね」のアニメーションCMが、一部のSNSユーザーの間で「性的表現を含む」として批判され、炎上する騒動に発展しました。
問題視されたのは、女性キャラクターが頬を赤らめる描写や、口元をアップで映す演出です。「男性視点で不快」「女性を性的に描写している」といった声が上がり、企業法務ナビや東洋経済オンラインでも取り上げられました。
しかし一方で、「過剰に反応しすぎ」「昔からある表現だ」といった擁護の声も多数見られました。料理研究家のリュウジ氏は、自身のXアカウントで「このアニメが性的だと話題らしいけど、炎上覚悟で言わせてもらうと一昔前のグルメ漫画で育ったから頬を染めて食うのはデフォルトだし全く性的に見えない」とコメントし、議論はさらに広がっています。
東洋水産はこの件に対して、謝罪やCMの削除などの対応を行わず、公式なコメントも発表しませんでした。
企業としてはあえて反応を控え、時間の経過とともに騒動の沈静化を待つ戦略を選んだと見られます。
結果的に、赤いきつねの炎上は比較的短期間で収束しました。
企業がとる炎上時の対応は、状況に応じて慎重に見極める必要があることを示す事例の一つです。
2.アサヒビールのKing & Princeいじり炎上(2024年)
2024年10月、アサヒビールが公式X (旧Twitter)アカウントで公開した新CMの予告投稿が、人気アイドルグループ「King & Prince(キンプリ)」の脱退騒動に関連するネットミームを連想させるとして、SNS上で炎上しました。
投稿内の文章に赤丸が付けられ、縦に読むと意味があるように見える「縦読み構文」が含まれていたことで、「ファンの気持ちを軽視している」「炎上を狙った悪質なマーケティングだ」といった批判が急増したのです。
一部のファンは不買運動を呼びかけるなどの行動に出るまでに至りました。
アサヒビールは翌日に問題の投稿を削除し、「配慮に欠けた表現」としてXに謝罪文を掲載しています。批判は一定期間続いたものの、迅速な対応を行ったことで、長期的な炎上には至っていません。
この事例は、SNS時代における企業の投稿は、意図しない誤解であっても大きな炎上につながるリスクを秘めていること、そして初動対応の重要性を示しています。
3.ほっかほっか亭「ライス販売停止」のSNS投稿が炎上(2025年)
2025年4月1日、ほっかほっか亭総本部の公式X (旧Twitter)アカウントにて、「米の価格が高騰しているため、全国のほっかほっか亭全店でライスの販売を停止する」という内容の投稿が行われました。
投稿には「#エイプリルフール」のハッシュタグが付けられていたものの、SNS上では「本当に販売を停止するのか」「誤解を招くような内容をエイプリルフールネタとして投稿すべきではない」などの批判が殺到したのです。
ほっかほっか亭の公式Xアカウントは、同日中に問題の投稿について「配慮が足りなかったと感じております。大変申し訳ございません。」という謝罪文を投稿しました。
また、同社の取締役が朝日新聞の取材に応じ、「反省しています」などのコメントを残しています。
一方で、謝罪の際の投稿には「国産米を100%使用している」という自社の強みを織り交ぜており、火消しとブランディングを同時に行う姿勢も見られました。
この事例は、エイプリルフール投稿の内容によっては予想以上の炎上リスクが潜んでいること、そして早期の謝罪と事実説明が炎上対策として有効であることを示しています。
4.人気ファッション誌「CLASSY.」の着回し企画が炎上(2025年)
2025年3月、女性ファッション誌「CLASSY.」が2月末発売号に掲載した「オペ看護師の着回し企画」が、SNSで炎上しました。
企画内のストーリーに「医師との不倫」要素が含まれていたことから、「医療従事者をバカにしている」「不倫を肯定する内容だ」などの批判が急拡大したのです。
この件は、FNNプライムオンラインなど複数メディアでも報道され、医療関係者や読者の反発を招きました。
「CLASSY.」編集部は、公式サイトにて2025年3月11日に謝罪文を掲載し、問題の経緯と今後の改善策を説明しています。
その結果、炎上は一定期間続いたものの、企画中止や雑誌廃刊には至りませんでした。
この事例は、特定の職業や立場に対する配慮不足が、信頼を損なう原因になることを示しています。
炎上対策としては、企画段階で多様な視点から表現を確認する社内チェック体制を構築し、専門家や当事者の意見を取り入れるなどの工夫が必要です。
5.ミツカンのSNS投稿「冷やし中華なんて…」が炎上(2025年)
2025年8月、ミツカンは公式X (旧Twitter)アカウントにて、「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです。」というコメントとともに、自社製品「冷やし中華のつゆ」だけをかけた具材なしの冷やし中華写真を投稿しました。(現在は削除されています)
夏休みシーズンと重なり、Xでは「夏休み中の料理」「家事の手間や負担」をテーマにした議論が活発化していた時期です。
その渦中でのミツカンの投稿は、「“なんて”という言い方が主婦の努力をバカにしている」「主婦や家庭で食事を準備する人を軽視している」と受け取られ、批判が一気に拡散したのです。
ミツカンは、数時間以内に問題の投稿を削除し、公式アカウントに謝罪文を掲載しました。素早い対応によって炎上は短期間で沈静化しましたが、たった一言の言葉遣いで炎上するリスクがあることを、改めて示した事例となりました。
SNSの炎上が企業に及ぼす影響
SNSの炎上は一度起きると、企業のブランドや事業活動に深刻なダメージを与えます。
- 売上・業績の低下
- 顧客・取引先からの信用の喪失
- 従業員の離職・内定辞退
炎上が長期化すれば、株価の下落や取引停止、経営全体に及ぶ損害へと発展しかねません。
そのため、初期対応を迅速かつ適切に行い、早期に沈静化を図ることが重要です。
売上・業績の低下
差別的な表現や配慮を欠いた広告、不適切な社員の発言などが原因で炎上すると、ブランドイメージが損なわれ、商品・サービスの購買意欲が大きく下がります。
実際、SNS上の不買運動や批判が数日で全国に広がり、販売数が急減した事例も少なくありません。
企業に直接の落ち度がなくても、誤情報や根拠のない噂が拡散されるだけで「炎上した企業」というレッテルが貼られ、売上や株価に影響するケースもあります。
顧客・取引先からの信用の喪失
SNSでの炎上により、炎上が取引先や顧客の信頼を揺るがすことは非常に多く、特にBtoB企業では契約打ち切りの要因となるリスクもあります。
迅速かつ誠実な説明や謝罪があれば「信頼できる企業」と評価されますが、対応が遅れたり不誠実な態度を取った場合、取引停止や契約解消につながりかねません。
従業員の離職・内定辞退
炎上内容が労働環境やコンプライアンス違反に関わる場合、従業員や内定者に不安が広がり、大量離職や内定辞退を引き起こすリスクがあります。
SNSでパワハラや長時間労働が告発されれば、たとえ一部の部署の問題でも企業全体の体質と見られやすく、採用活動にも大きな影響が出るでしょう。
従業員向けのSNS利用ガイドラインや内部通報窓口を整備するなど、社内の透明性を高める対策が必要です。
炎上予防のために取り組むべき対策

企業が公式SNSを運用する際は、炎上してから火消しを行うだけでなく、そもそも炎上を起こさない仕組みを作ることが重要です。
続いては、企業が炎上予防のために取り組むべき具体的な対策方法をいくつか紹介します。
SNSの運用マニュアルを作成する
企業公式アカウントを複数の担当者が扱う場合、投稿ルールや緊急時の対応が曖昧だと炎上の火種になりかねません。
投稿してはいけないNG表現、個人情報の扱い方、外部からの問い合わせ対応手順などを明確にまとめた運用マニュアルを作成しておくことが重要です。
関連記事:SNSガイドライン・ポリシー策定の目的とは?必要な9項目と事例紹介
従業員へ研修で炎上リスクや予防法を伝える
アカウント運用を担当する従業員はもちろん、個人でSNSを使用している従業員一人ひとりに、炎上がもたらす影響について正しく理解してもらうことが炎上対策の基本です。
社員の個人投稿が原因で企業に批判が集まるバイトテロや内部告発型炎上も後を絶ちません。
そのため、新入社員研修や定期研修で、炎上が及ぼす経済的損失や信用低下の事例を共有し、社内全体にSNSリテラシーを浸透させることが効果的です。
エルプランニングでは、専門コンサルタントによる「SNSリスクリテラシー研修」を提供しています。
業種や規模、対象者(新入社員、管理職、SNS担当など)ごとにオーダーメイド研修のご提案も可能です。
コンテンツ公開前にチェックを行う
SNS投稿は一度公開すると瞬時に拡散され、削除しても完全には取り戻せません。
公開前に複数人で内容を確認する「ダブルチェック」「トリプルチェック」を導入しましょう。
特にジェンダーや社会問題に関連する内容は敏感に受け取られやすいため、専門知識を持つメンバーを含めることが望ましいです。
モニタリングで炎上を早期発見する
どれほど注意しても、ユーザーからの批判や根拠のない噂が拡散する可能性はゼロではありません。
自社名や商品名、関連キーワードを日常的にモニタリングし、ネガティブワードが急増した際に即対応できる体制を整えましょう。
エルプランニングでは、官公庁への導入実績も誇る「ネット監視サービス」を提供しています。24時間体制での監視や万一の炎上時サポート保険など、より強固な炎上対策が可能です。
炎上の火種を早期に発見できれば、事態が大きくなる前に対処できる可能性が高まります。
炎上への対応フローを作っておく
予防が最優先ではあるものの、完全に炎上を防ぐことはできません。
万が一の際に備え、初動対応から公式声明発表までのフローを事前に策定しておくことが重要です。
- 監視担当者が異常を検知
- 広報・法務・経営陣が事実確認
- 謝罪や情報開示のタイミングを判断
など、具体的な手順をマニュアル化して社内共有しておくことで、混乱を防ぎ、被害を最小限に抑えられるでしょう。
SNSが炎上してしまったときの対処法
残念ながら、どれだけ注意していても、炎上の可能性はゼロにはなりません。
万が一に備え、適切な炎上対策を理解しておくことは、被害を最小限に抑える鍵となるでしょう。
続いては、自社のSNSが炎上した場合に取るべき行動と対処のポイントを具体的に解説します。
関連記事:炎上対応ガイド:リスクを最小限に抑えるための対策と手順
安易な投稿削除はNG
問題の投稿をすぐに削除すると「隠蔽」「逃げた」と受け取られ、かえって批判が拡散する危険があります。
まずは事実関係を整理し、謝罪や説明とセットで削除するのが基本です。
削除する場合も、削除理由を明確に発表しておくと、ユーザーからの理解を得やすくなります。
社内共有と事実確認
自分がSNSアカウントの運用担当者だとしても、一人で対処しようとするのは危険です。
速やかに上司や広報・法務・経営陣など関係部署へ報告しましょう。
初動で事実確認を怠ると、対応が二転三転し、さらなる炎上を招く場合があります。
炎上の原因、批判の内容、拡散状況を正確に把握することが重要です。
謝罪・状況説明
批判が高まっている場合は、誠実な謝罪と状況説明をできるだけ早く発信しましょう。
事実を正確に伝え、再発防止策に言及することで、信頼を回復しようとしているという姿勢が伝わります。
曖昧な表現や言い訳は逆効果となるため、文面は慎重に作成してください。
投稿内容の削除
謝罪と説明を行った後、問題の投稿を削除する判断をします。
炎上への対応プロセスの一環としての削除であれば、批判の沈静化を早める効果が期待できるでしょう。
スクリーンショットなどで投稿が残る可能性を前提に、削除後も説明責任を果たす姿勢を示すことが重要です。
炎上の再発防止対策
何度も炎上すれば、企業のイメージはさらに損なわれることとなります。
再炎上しないよう、炎上に至った経緯や問題点を洗い出し、対策を講じることが大切です。
- 投稿前の多重チェック体制の導入
- 社員向けSNSリテラシー研修
- ネット監視サービスによる常時モニタリング
など、社内体制を整備することが、再炎上の防止につながります。
SNS炎上はどの企業にも起こり得る!研修や監視で炎上対策をしよう

SNS炎上は業種や規模を問わず、あらゆる企業に起こり得るリスクです。
しかし、炎上を恐れて運用を避ければ、ブランド認知や顧客との接点など貴重なマーケティング機会を逃してしまいます。
重要なのは、炎上を未然に防ぐ仕組みと、万が一発生した際の迅速な対応体制を整えておくことです。
エルプランニングでは、従業員向けの「SNSリスクリテラシー研修」や、口コミ・SNS投稿をツール+有人体制で監視・分析する「ネット監視サービス」を提供しています。
日常的なモニタリングから緊急時の対応までトータルでサポートし、企業のSNS活用を安心して進められる環境づくりを支援しています。
SNSアカウント運用に伴う炎上対策については、エルプランニングまでお気軽にご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。