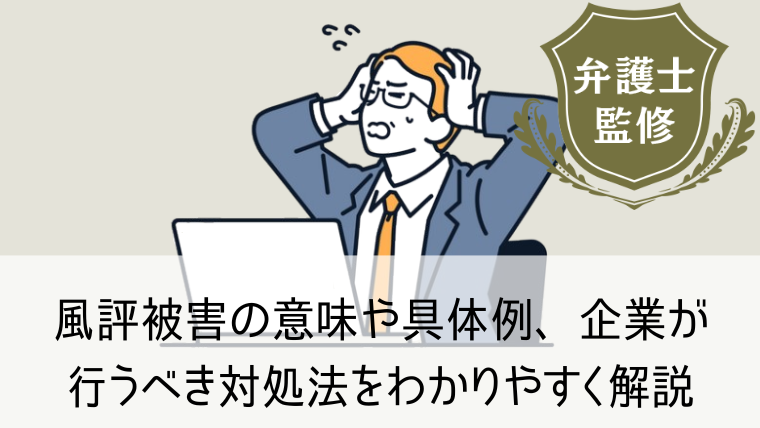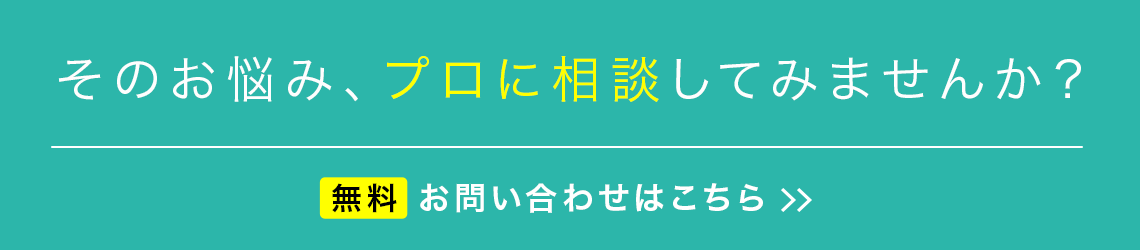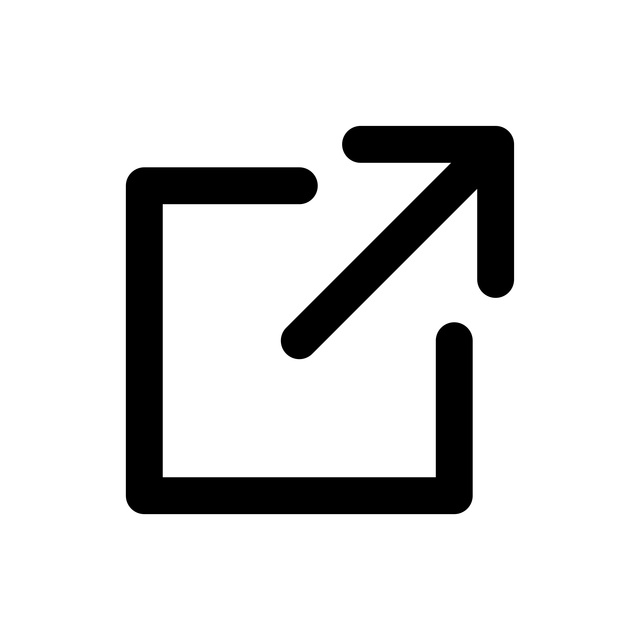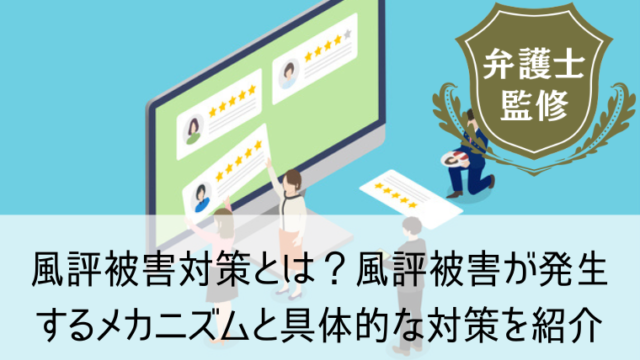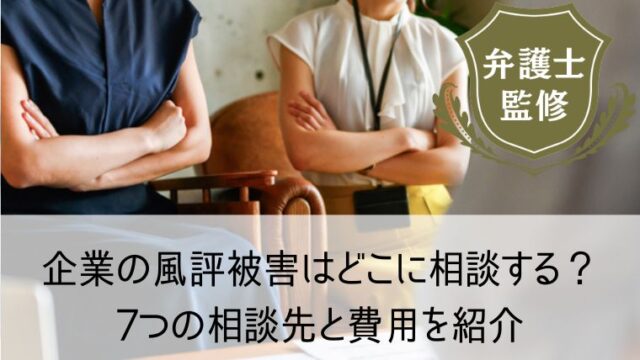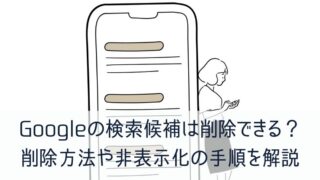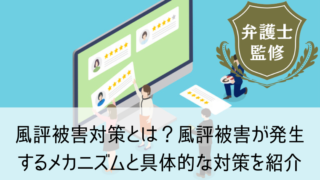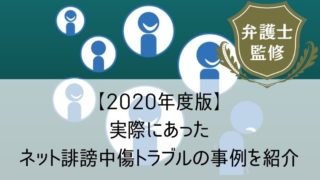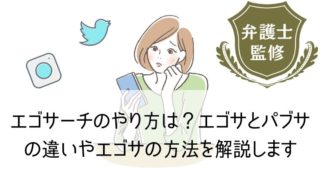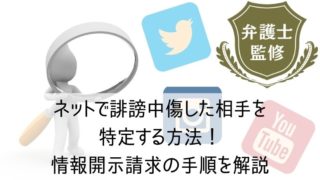インターネットやSNSの普及により、根拠のない噂や誤情報が一気に拡散され、企業の信用や売上に深刻な影響を及ぼす「風評被害」が社会問題となっています。
実際には事実と異なる情報であっても、消費者や取引先に誤解を与え、経営に甚大なダメージを与えるケースも少なくありません。
この記事では、風評被害の正確な意味や代表的な事例を紹介しながら、企業が取るべき対処法についてわかりやすく解説します。
風評被害の正しい意味
風評被害とは、根拠のない噂や誤解に基づいた情報(風評)が、インターネットや口コミなどで広まり、企業や個人の信用・評判が損なわれることで、経済的・社会的な損害を受けることを指します。
SNSや掲示板、レビューサイトなど、誰でも簡単に情報を発信できる現代では、風評被害が急速に拡大するリスクが高まっています。
ただし、「風評」と「正当な評価」は明確に区別する必要があります。
例えば、実際に不良品が届いた顧客が、その体験をもとにレビューで不満を述べる行為があった場合、それが企業にとってネガティブな内容であったとしても、事実に基づいていれば風評被害には該当しません。
一方で、「あの商品は体に悪いらしい」「あの会社はブラック企業だと聞いた」といった裏付けのない発言が拡散された場合、これは風評被害となり得るでしょう。
虚偽の情報を拡散する行為は、名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪などの法的責任を問われる可能性もあります。
企業としては、事実に基づく指摘を真摯に受け止める一方で、明らかに虚偽とされる情報には、法的措置を含めた冷静かつ迅速な対処が必要になるでしょう。
信頼を守るためにも、日頃から正確な情報発信と風評対策の体制を整えておくことが大切です。
風評被害をもたらす情報の種類

続いては、風評被害を引き起こす主な情報の種類について詳しく解説します。
根拠のない噂やデマ
もっとも典型的な風評被害の例は、事実に基づかない憶測や「あの商品は危険らしい」といった伝聞情報の拡散です。
これらは確認されていない情報であるにもかかわらず、「○○と聞いた」「○○の噂がある」といった形で広まりやすく、真偽の判断が難しい情報ほど不安をあおります。
一度広まってしまうと、企業が公式に否定しても信じてもらえず、ブランドイメージの低下や売上減少といった実害につながり、被害が長期化するおそれもあるでしょう。
SNSや掲示板での誹謗中傷
X(旧Twitter)や匿名掲示板、YouTubeコメント欄などでは、特定企業や担当者を名指しした誹謗中傷が投稿されることがあります。
投稿は拡散力が非常に高く、短時間で多くの人の目に触れるため、影響範囲が大きくなりやすいのが特徴です。
内容が事実無根であっても、印象だけが一人歩きし、企業イメージを大きく損ねるリスクがあります。 また、投稿者が匿名のため悪質化しやすく、削除対応や法的措置が追いつかないケースも存在します。
ニュース報道の誤解や誇張
一見すると信頼性の高いマスメディアの報道でも、編集の仕方によっては誤解を生むことがあります。
発言の一部だけを取り上げて報道したり、見出しを過激な表現に変えたりすることで、本来の意図とは異なる印象を与えてしまうでしょう。
事実と異なるイメージが独り歩きすることで、風評被害が拡大するリスクが増大します。
消費者の口コミやレビューの誤情報
レビューサイトやSNSに投稿される消費者の意見は、購買判断に大きく影響します。
事実に基づかない投稿や、誤認による苦情が拡散された場合、他のユーザーの判断を誤らせ、企業の評判に大きなダメージを与えるでしょう。
例えば、実際には発生していないトラブルが、あたかも事実であるかのように広まると、企業の評判を著しく損ない、深刻な風評被害につながるおそれがあります。
意図的な情報操作
競合他社や悪意のある個人が、意図的に企業の評価を下げる目的で行う情報操作も深刻な問題です。
偽アカウントを使ってネガティブな書き込みを繰り返したり、自作自演で悪い口コミを投稿したりする手法は、特にECサイトや口コミプラットフォーム上で見られます。
このような行為は、名誉毀損や侮辱、業務妨害に該当する可能性があり、法的措置が検討されることもあります。
風評被害が企業に与える影響
風評被害は、企業の経営活動に多方面で深刻な影響を及ぼします。
単なる一時的な評判の低下にとどまらず、企業全体に長期的なダメージをもたらす可能性もあるでしょう。
ここでは、風評被害が企業に与える代表的な影響について、具体的に解説します。
売上や顧客数の減少
企業や製品に対する悪評がネットやSNSを通じて広まると、消費者の不信感が高まり、購買意欲が低下します。
例えば、「この会社の商品は危険らしい」「あの店の対応がひどかった」という投稿が拡散されることで、来店者数やオンラインでの注文数が激減した事例もあります。
さらに、1つの商品やサービスに関する悪評が、企業全体のイメージを損ない、他の部門の商品の売上にまで悪影響を及ぼすケースも珍しくありません。
取引先やパートナー企業からの信頼低下
風評は消費者だけでなく、取引先やパートナー企業にも波及します。
「信用リスクのある企業と取引するのは避けたい」と判断され、主要な仕入先から契約更新を拒否されたり、新規取引の話が白紙になった事例もあり、仕入れや販売ルートの見直しを迫られる可能性もゼロではありません。
ネットやSNS上の悪評が原因で、取引の停止や縮小が続けば、売上減少や業績悪化といった経営面での深刻な被害につながります。
従業員の士気や採用への悪影響
企業に対する誹謗中傷が社内にまで伝わると、従業員のメンタル面に影響を与え、仕事へのモチベーションが低下するおそれがあります。
「SNSで社名を検索したら悪口ばかりだった」という事例もあり、離職者の増加や社内の雰囲気悪化につながることもあるでしょう。
また、企業の評判は求職者にも大きく影響するため、採用活動が難航し、優秀な人材確保が困難になるリスクもあります。
株価の下落や投資家離れ
上場企業にとって、風評は株価の下落や投資家の信頼喪失につながる懸念があります。
SNSでの炎上やメディア報道をきっかけに、株価が急落することも珍しくありません。
企業が迅速かつ適切な対応を行わなければ、情報の真偽を問わず、市場からネガティブに評価されてしまうのです。
その結果、投資家に不信感を与え、株主離れにより新たな資金調達が困難になるといった財務面への影響が生じることもあります。
長期的なブランド価値の毀損
企業のブランドイメージは、長年の努力と信頼の積み重ねによって形成されます。
しかし、風評被害によって一瞬で崩れ去ることがあるのも事実です。
一度傷ついたブランドイメージを回復するのは容易ではなく、例え事実無根であっても「なんとなく悪い印象がある」といった感情が、消費者に残り続けることがあります。
このような状態が続けば、ブランド価値の低下が固定化され、再起に時間とコストがかかることは避けられません。
企業が風評被害に遭ったときの対処法

正しい対処を行えば信用回復やブランドの再構築につながりますが、対応を誤ると被害が長期化し、企業活動に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。
ここでは、風評被害に対して企業が取るべき基本的な対処法について、順を追って解説します。
事実確認と迅速な情報収集
最初に行うべきは、社内外の情報を速やかに収集し、事実関係を正確に把握することです。
投稿や報道内容の出所、拡散の経路、影響範囲などを調査し、どこに誤解や誤情報が含まれているかを明確にします。
また、社内の関係部署からもヒアリングを行い、問題の発端や過去の対応履歴なども整理しておくことが重要です。
ここでの遅れや判断ミスが、後の対応の信頼性を左右します。
公式な声明や謝罪文の発信
状況が把握できたら、速やかにステークホルダーに向けた公式な声明を発信します。
問題が事実である場合は、誠意ある謝罪と再発防止策を明示することで、信頼回復の糸口になるでしょう。
逆に、事実無根の誤情報である場合は、毅然とした態度で明確に否定し、誤解を払拭する必要があります。
これにより、さらなる風評被害の拡大を防げるでしょう。
SNSやメディアを通じた正確な情報発信
事実無根であることを公表したら、公式サイトやX(旧Twitter)・InstagramなどのSNSを活用し、正確な情報を広く発信しましょう。
放置すれば誤情報が事実のように受け取られてしまうため、情報発信のスピードが重要です。
「沈黙は肯定と見なされる」というネット上の風潮を考慮し、疑念を放置しない姿勢が求められます。
法的措置の検討と弁護士への相談
明らかに悪意のある投稿や企業の信用を傷つけるデマには、名誉毀損罪・信用毀損罪・業務妨害罪などの法的措置も検討しましょう。
該当する投稿のスクリーンショットやURL、日時などの証拠を確保し、インターネットトラブルやIT関連の風評被害に詳しい弁護士に相談するのが効果的です。
社内体制の見直しと再発防止策の構築
風評被害を未然に防ぐためには、日頃からの危機管理体制が重要です。
広報や法務と経営層が連携し、トラブル発生時の対応フローやメディア対応マニュアルの整備を進めておくと、万が一の際にも落ち着いて対応できます。
また、従業員の情報リテラシーを高めることも、再発防止への第一歩です。
SNSでの不用意な投稿が炎上や情報漏洩、風評被害につながることへの理解を深める「SNSリスクリテラシー研修」の実施が効果的です。
風評被害への理解を深めて正しく対処しよう
風評被害は、企業の規模や業種に関係なく、誰にでも起こりうるリスクです。
インターネットやSNSが普及した現代では、根拠のない噂や誤情報が一気に拡散され、売上の減少、顧客離れ、取引停止、株価の下落など、深刻な経営ダメージを引き起こす可能性があります。
このような風評被害に備えるためには、正しい知識を持ち、平常時から情報管理体制を整えておくことが重要です。
万が一トラブルが発生した際にも、事実確認、情報発信、必要に応じた法的措置を迅速に講じることで、被害の拡大を最小限に抑えることができるでしょう。
エルプランニングの風評被害対策サービスでは、ネット上に広がる誤情報やネガティブな検索結果に対応し、企業ブランドの保護・回復をサポートしています。
経験豊富な専任コンサルタントが状況に応じて柔軟に対応策を提案いたします。
独自の対策手法により、より効果的に企業イメージの改善を図ることが可能です。
風評被害は「放置せず、早く動く」が最善の対処法です。
24時間体制でご相談を受け付けておりますので、少しでも不安を感じたらぜひお早めにご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。