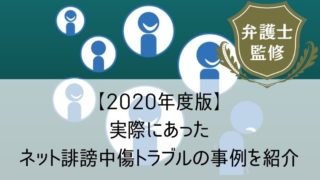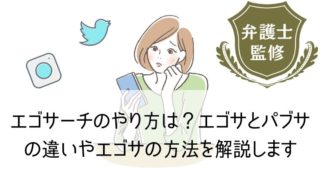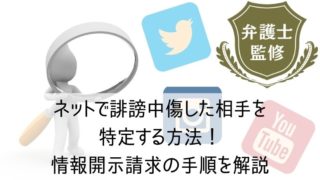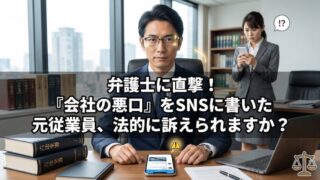近年、飲食店や小売店などで従業員が勤務中の不適切な行為をSNSに投稿し、企業の信用を大きく損なう「バイトテロ」が社会問題となっています。
一度拡散されると、店舗の閉鎖や損害賠償、企業ブランドの失墜にまで発展するケースもあり、企業にとっては深刻なリスクです。
スマートフォンが広く普及し、多くの人がSNSを利用している現代において、バイトテロは業種や規模を問わず、どの企業でも起こり得ます。
従業員教育や情報発信ルールの整備など、具体的な対策を講じておくことが重要です。
この記事では、近年発生したバイトテロの主な事例を紹介し、発生時の対応方法や未然に防ぐ対策について詳しく解説します。
バイトテロとは

バイトテロとは、アルバイト従業員が勤務中に不適切な行為を行い、その様子をスマートフォンで撮影してSNSに投稿し、炎上を引き起こす行為のことです。
過去には、飲食店での不衛生な行動や、コンビニでの商品を粗末に扱う様子が拡散され、店舗閉鎖や損害賠償に発展したケースもあります。
このような行為は、たとえ「軽い悪ふざけ」として投稿されたものでも、瞬く間に全国へ拡散され、企業の信用を大きく損なう結果を招きます。
被害は店舗だけでなく、フランチャイズ本部全体に及ぶこともあり、企業のブランド価値や採用活動にも深刻な影響を与えるでしょう。
企業イメージや評判を大幅に下げるリスクを持っていることから、「テロ」という名称が使われ、問題視されています。
実際に起きたバイトテロの事例5つ
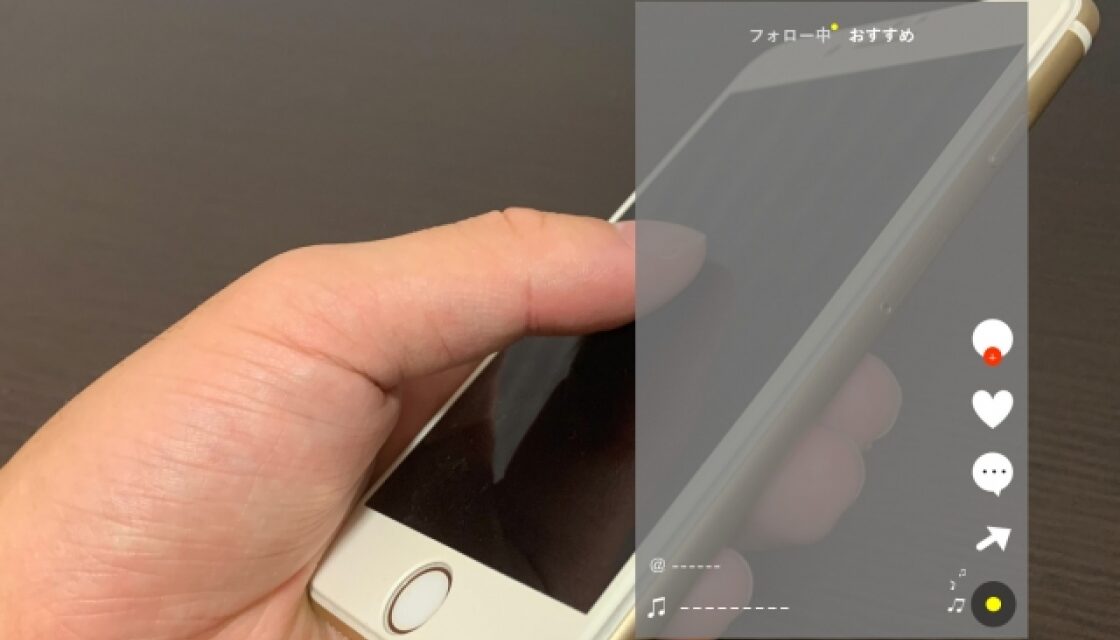
ここからは、実際に報道でも取り上げられたバイトテロの代表的な事例を5つ紹介します。
1.しゃぶ葉店員がホイップクリームを口に直接流し込み炎上(2024年)
2024年2月、すかいらーくホールディングスが運営する「しゃぶ葉」で、アルバイト同士がふざけて、業務用ホイップクリームを口に直接流し込む様子を撮影した動画がSNS上で拡散されました。
店内の厨房で撮影されたこの動画では、1人の従業員がもう1人を押さえ込みながら、食品を直接口に入れるという不適切な行為が映っており、視聴者から「不衛生」「企業としての教育体制に問題がある」と非難の声が相次ぎました。
同社は即日謝罪文を発表し、当該店舗を一時休業とする対応を取りました。
公式発表では「当該動画は2月2日の閉店後、廃棄予定であったホイップクリームを使用して撮影されたものであり、お客様に提供された食材ではないことを確認しております」と明記し、謝罪しています。
しゃぶ葉のバイトテロ事例は、産経新聞や読売新聞などでも報道されました。
2.カレーハウスCoCo壱番屋店員が賄いのカレーに体毛を入れ炎上(2021年)
2021年6月、人気カレーチェーン「CoCo壱番屋」で勤務する男性アルバイトが、まかない用のカレーに自分の体毛を混入させる動画を撮影し、Instagramのストーリーズに投稿しました。
鍵付きアカウントで24時間以内に消える投稿でしたが、流出して拡散され、SNS上で批判が殺到した事例です。
店舗を運営するCoCo壱番屋は、「お客様に不快な思いをさせたことを深くお詫び申し上げます」とコメントを発表し、関係者を厳重に処分しました。
CoCo壱番屋のバイトテロは、読売新聞オンラインやJ-CASTニュースでも大きく取り上げられ、多くの企業でまかない時の衛生管理や、個人SNSの利用ルールを改める動きが広がりました。
3.ファミリーマート店員がホットスナックケースでモップを乾燥させて炎上(2024年)
2024年10月、ファミリーマートの店舗で「洗ったモップをホットスナックのケース内で乾燥させている」という画像がX(旧Twitter)で拡散されました。
投稿を行ったのは店員本人ではなく、偶然現場を目撃した来店客でしたが、衛生管理がずさんだとして非難が殺到しています。
さらに、一部の投稿が「外国人従業員による行為」として拡散されたことから、SNS上では偏見を助長するコメントが相次ぎ、騒動はさらに拡大しました。
ファミリーマート本部は即座に謝罪と事実確認を行い、該当店舗の営業を停止して衛生状態を点検すること、再発防止策として全店舗への衛生教育を再徹底することを発表しました。
ライブドアニュースやJ-CASTニュースでも報じられ、SNS時代における風評被害のリスクを改めて浮き彫りにしています。
4.ドミノ・ピザ店員が鼻の穴に入れた指をピザ生地にこすりつけ炎上(2024年)
2024年2月、大手宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」の店舗で、アルバイト従業員が自身の指を鼻の穴に入れた後、そのままピザ生地にこすりつける動画を撮影し、SNSに投稿しました。
動画は当初、本人がInstagramの鍵付きアカウントに限定公開していたものの、何らかの形で流出し、拡散されました。大手メディアでも取り上げられ、大きな批判を招く結果となっています。
ドミノ・ピザを運営する株式会社ドミノ・ピザジャパンは即日謝罪し、当該店舗を一時閉店しています。また、該当従業員を懲戒処分としたうえで、全店舗に衛生管理とSNS利用に関する再教育を実施しました。
ドミノ・ピザのバイトテロは、飲食業界全体に対し「一人の不適切な行為が企業全体の信頼を失墜させる」という教訓を与え、東洋経済オンラインや読売新聞オンラインでも詳しく報じられました。
5.ファミリーマート店員がバックヤードのモニターで女性客の胸元を凝視し炎上(2021年)
2021年6月、ファミリーマートの店舗で、防犯カメラのモニターを見ながら女性客の胸元を注視する複数の男性従業員の様子がSNSで拡散され、批判が殺到しました。
この動画は来店客が偶然撮影したもので、食品衛生面の問題ではなく、職場でのモラルや人権意識の欠如が問われる事例として大きな波紋を呼んでいます。
ファミリーマート本部は事実確認のうえ、関係従業員を処分し、再発防止策として全店舗でのカメラ管理ルールの見直しと従業員教育を徹底しました。
日テレNEWS NNNやJ-CASTニュースなどでも報道され、SNS時代における倫理問題の代表例として注目されました。
バイトテロはなぜ起こる?
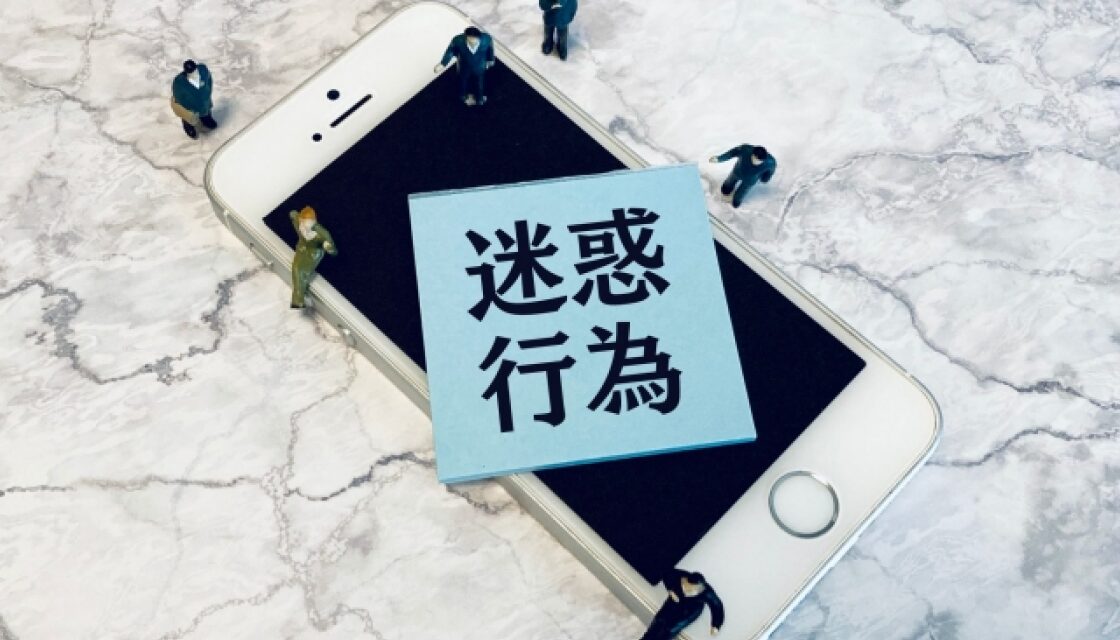
バイトテロが起こる背景には、SNSの影響や若者のネットリテラシー不足だけでなく、職場環境や企業の教育体制など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
ここでは、バイトテロが起こる4つの原因について、詳しく見ていきます。
SNSの急速な普及
スマートフォンが普及する以前にも、職場での悪ふざけ自体は存在していましたが、当時はその場限りで済むことがほとんどでした。
しかし現在では、動画を撮影してSNSに投稿すれば、数分で全国的に拡散され、企業の信用を一瞬で失墜させる事態に陥っています。
特に、近年のバイトテロでは、鍵付きアカウントやストーリーズといった限定公開機能を過信し、内部の動画を軽い気持ちで投稿するケースが多く見られます。
一度ネットに出た情報は完全に消すことが難しく、友人だけのつもりが大炎上につながるリスクを正しく理解できていない点が問題です。
若者のネットリテラシーの低さ
スマートフォンやSNSの普及は急速に進み、誰もが気軽に情報を発信できる時代になりました。
しかし、そのスピードに対してネットリテラシー教育が必ずしも追いついているとはいえません。
総務省の「青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査結果」によると、不適切投稿や炎上など、有害情報リスクに関するILASテスト結果の正答率は、71.5%となっています。
SNSを安全に利用するための教育は学校現場でも増え始めているようですが十分とはいえず、企業側の研修や啓発活動も積極的に実施するのが適切と言えるでしょう。
従業員への教育不足
バイトテロを防ぐには、従業員一人ひとりにSNSリテラシーと職業倫理を正しく理解させることが重要です。しかし、実際にはアルバイト採用時や新人研修で、SNSリスクに関する教育が十分に行われていないケースは少なくありません。
特に学生アルバイトが多い職場では、SNSでの発信を日常の延長と捉えてしまい、軽い気持ちで動画を撮影・投稿することが問題視されています。
SNS投稿が企業の信頼に与える影響を具体的に伝える教育が行われていれば、「バイト中に動画を撮影してはいけない」「不適切な動画をSNSに投稿してはいけない」という意識を持てるようになるでしょう。
また、ファミリーマートでのモップ乾燥事例のように、従業員本人の行為でなくても、第三者が不衛生な光景を撮影・拡散し、炎上につながることもあります。
SNS投稿への意識づけだけでなく、衛生教育も含めた研修やチェック体制の強化が、リスク回避の第一歩です。
従業員の不満やストレス
単なる悪ふざけではなく、職場への不満や上司・同僚への反発が原因で、意図的にバイトテロを起こすケースもあります。
「給料が低い」「シフトが厳しい」「人間関係が悪い」などの不満が蓄積し、ストレスのはけ口として問題行動に走ってしまう可能性もあるでしょう。
「どうせ辞めるなら一矢報いたい」といった心理が働くこともあります。
企業側は、不満やストレスが炎上につながる前に、相談体制や定期的な面談を設け、従業員とのコミュニケーションを密にすることが重要です。
バイトテロが企業や店舗に与える影響

バイトテロは一瞬の行為で終わらず、企業に長期的な損害を与えるリスクがあります。
ここでは、代表的な影響を見ていきましょう。
企業のイメージや信頼が損なわれる
バイトテロによって企業が受ける最大のダメージは、長年かけて築いたブランドイメージや顧客からの信頼を失うことです。
一度炎上が発生すると、SNSやニュースサイトで過去の不祥事とともに拡散され、企業の印象が著しく低下します。
実際に、バイトテロをきっかけに上場企業の株価が急落したり、謝罪会見を余儀なくされた事例もあります。
参考:Bloomberg「くら寿司にバイトテロの影響じわり、株価は1月末比27%安」、ITmediaビジネスオンライン「「バイトテロ」「バカッター」が存在する、3つの背景:新連載・炎上の火種」
集客や売上がダウンする
現代では、多くの消費者がSNSや口コミを参考に店舗や商品を選ぶため、ネット上での評判が売上を大きく左右します。
バイトテロに関するネガティブな投稿が拡散されれば、「衛生的に不安」「企業体質に問題がある」と感じた顧客が離れ、集客減少や売上低下を招きかねません。
さらに、フランチャイズの場合は、無関係の加盟店まで風評被害を受けるリスクがあり、経営全体に深刻な打撃を与えることもあります。
事実確認や謝罪対応に追われる
SNSで拡散された情報は瞬時に広まります。企業が初動の対応を誤ると、「対応が遅い」「誠意が感じられない」といった批判が相次ぎ、さらなる炎上に発展することも多いです。
そのため、バイトテロが発覚すると、企業は真偽の確認や原因究明、謝罪対応に追われることになります。
また、事実確認や謝罪対応には、スタッフの人件費や弁護士費用、信頼回復のための広告出稿費用など、本来必要のないコストや手間がかかります。
さらに、加害従業員への損害賠償請求手続きや店舗の一時休業により、経営面での損失も避けられません。
一度の悪ふざけが数百万円単位の損害に発展するという現実は、企業にとって深刻なリスクとなります。
人材確保が困難になる
バイトテロによる炎上は、社内外の信頼関係にも悪影響を及ぼします。
従業員の士気が低下し離職を希望する人が増える傾向があります。
特に接客業や飲食業では、炎上した店舗に新しいスタッフが応募しづらくなり、人手不足が深刻化することも少なくありません。
また、企業ブランドに不祥事のイメージが残ると、採用活動全体にも影響します。
真面目に働いていた従業員が離職し、代わりの人材を確保できないまま店舗運営が困難になってしまうでしょう。
バイトテロは一時的な炎上にとどまらず、長期的リスクにつながる可能性があります。
バイトテロを未然に防ぐための対策

バイトテロは一度発生すると、企業や店舗の信用を大きく損ない、売上や採用活動にも長期的な影響を及ぼします。
発生後の火消しはもちろん、発生させないための予防策を徹底することが重要です。
ここでは、企業や店舗側が今すぐ実践できる具体的なバイトテロ対策を4つ紹介します。
従業員向けの研修や勉強会を行う
バイトテロの多くは、悪意というよりも「軽い気持ち」や「SNSの影響力を理解していない」ことが原因で起きています。
特に若年層は、日常的にSNSを利用しているにもかかわらず、ネット上での発信に伴う法的リスクや社会的責任を深く理解していないケースが多いです。
そのため、定期的に従業員向けのネットリテラシー研修を実施し、SNS投稿の危険性や炎上の実例を共有することが効果的です。
【ネットリテラシー研修で取り上げたい内容】
- 炎上の仕組みと拡散スピード
- SNS投稿による信用失墜の実例
- 投稿者本人が負う法的責任と企業への影響
ネットリテラシー研修では、単に「投稿禁止」と伝えるだけでなく、「なぜそれが問題なのか」を理解させることがポイントです。
例えば、過去に飲食店で発生した炎上動画の事例を紹介し、どのようにブランド価値が失われたかを具体的に説明すると、より当事者意識を持たせられます。
また、アルバイトの入れ替わりが激しい職場の場合、一度きりの研修では不十分です。
新人が入るタイミングや繁忙期前など、定期的に開催することをおすすめします。
エルプランニングでは、風評被害対策の専門コンサルタントによる、オーダーメイド型のSNSリスクリテラシー研修をご提供しております。
当社の研修は、民間企業はもちろん、官公庁や学校法人などでの開催実績があり、実施後アンケートの満足度は98%と高い評価をいただいているのが強みです。
SNS利用に関するガイドラインを策定する
炎上リスクを事前に抑えるためには、日頃から全スタッフへ周知することが重要です。
研修と並行して、SNS利用に関する明確なルールを定めた「ガイドライン」を整備しましょう。
以下のようなルールを盛り込むと効果的です。
- 店内での写真・動画撮影の禁止
- 業務スペースへのスマートフォン持ち込み禁止
- 制服着用時のSNS投稿制限
- 企業情報や顧客情報の取り扱いなど
ガイドラインは単なる注意喚起ではなく、企業としての信頼を守るための規律であることを明確に伝える必要があります。
就業規則の一部として位置付け、違反した場合の処分基準(減給・契約解除など)を明記しておきましょう。
従業員の労働環境を改善する
バイトテロの背景には、職場への不満やストレスの発散が動機になっているケースも少なくありません。
労働条件が厳しかったり、上司との人間関係が悪かったりすると、従業員の不満が蓄積し、結果的に職場や企業への反発行動につながる可能性があります。
バイトテロを防ぐには、就業規則などのルールで縛るだけでなく、働きやすい職場づくりを意識することが大切です。
具体的には、以下のような取り組みを行うとよいでしょう。
- 従業員の労働環境に課題がないか、定期的にヒアリングやアンケートで確認する
- 定例ミーティングでアルバイトの意見や悩みを吸い上げ、改善策を早期に実行する
- 正社員とアルバイトの間に壁を作らず、意見交換ができる環境を整える
特に飲食業や小売業など人手不足の業界では、不満の放置が退職や炎上の引き金になることもあるため、早めの対応が重要です。
職場環境の改善は、離職率の低下やサービス品質の向上にもつながり、結果的にバイトテロの防止策となります。
監視システムを導入する
バイトテロの多くは、SNSでの投稿がきっかけで発覚し、瞬く間に拡散してしまいます。
特にX(旧Twitter)やInstagram、TikTokなどでは、匿名の第三者によって不適切な動画や写真が投稿されるケースも多く、企業側が気づいたときにはすでに大炎上していることも珍しくありません。
炎上リスクを最小限に抑えるには、ネット監視サービスの導入が効果的です。
エルプランニングでは、口コミやSNS投稿を24時間体制で監視し、炎上リスクを可視化・分析できる「ネット監視サービス」を提供しています。企業名や店舗名、商品名などを常時モニタリングし、炎上の兆候を検知します。不適切な投稿を早期に検知することで、被害の拡大を防止するための初動対応を迅速に行うことが可能です。
万が一炎上が発生した場合でも、「火消し対応費用」として最大500万円までが補償されるため、リスクマネジメントの一環として安心して導入いただけるでしょう。
ネット監視サービス
バイトテロの事例から学び、未然に防ぐ方法を実践しよう!

スマートフォンとSNSが身近になった現代では、些細な悪ふざけが一瞬で拡散し、企業の信用を失墜させる事例が後を絶ちません。
この記事で紹介したバイトテロの事例はほんの一部であり、ほかにも多くの事例が発生しています。
一度炎上すると、その後の謝罪や損害対応に追われるなど、被害は想像以上に深刻です。
バイトテロを防ぐには、従業員一人ひとりのネットリテラシーを高めることが重要です。
あわせて、SNS利用のガイドライン策定や職場環境の改善、監視システムの導入など、総合的なリスクマネジメントが求められます。
まずは、定期的な研修や勉強会の開催など、すぐに実行できる対策から始めてみてはいかがでしょうか。
従業員教育と監視体制を整えておくことで、バイトテロを未然に防ぎ、信頼される企業づくりにつながります。
エルプランニングでは、SNSリスクリテラシー研修やネット監視サービスなど、企業を守るためのサービスを複数提供しております。
バイトテロやSNS炎上を未然に防ぐ対策として、ぜひ導入をご検討ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

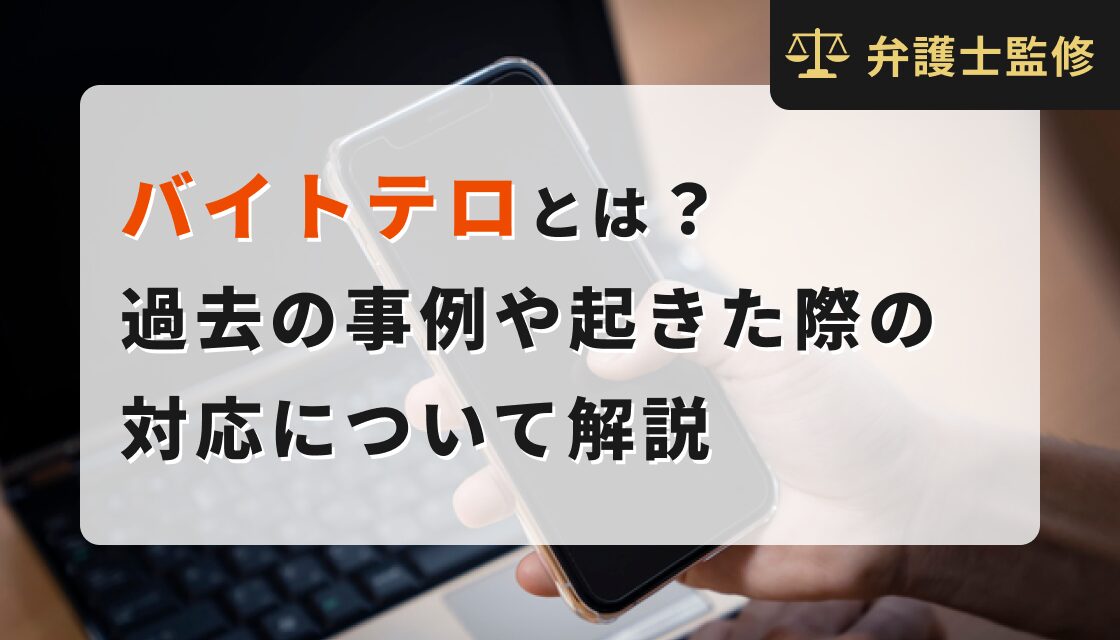
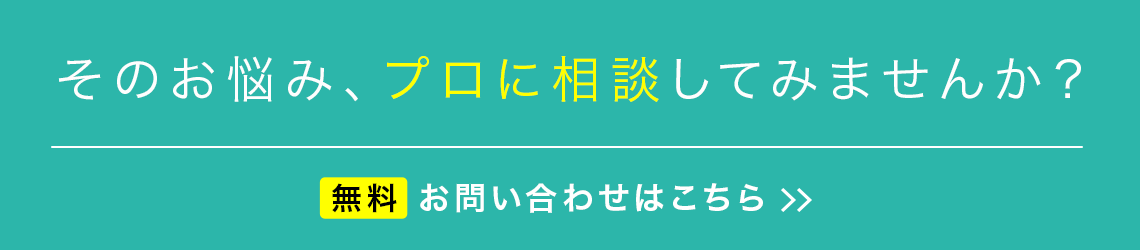

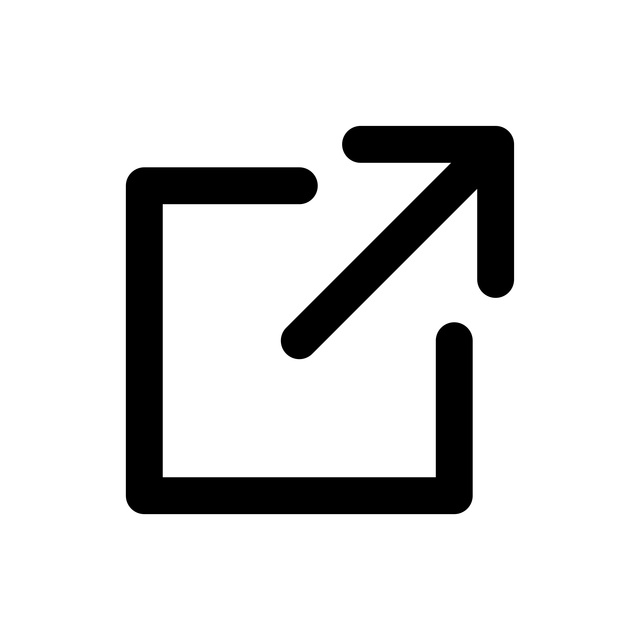


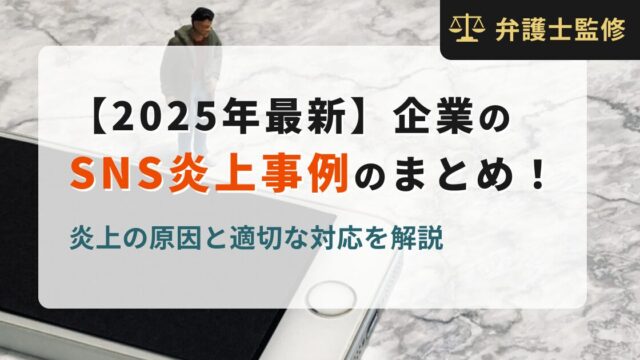

-320x180.jpg)