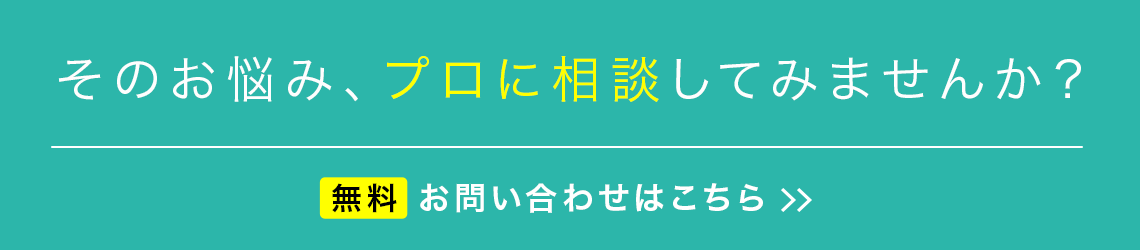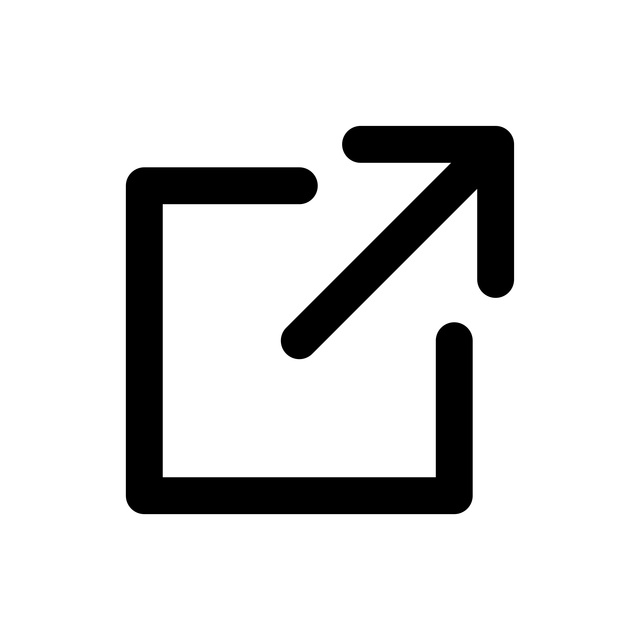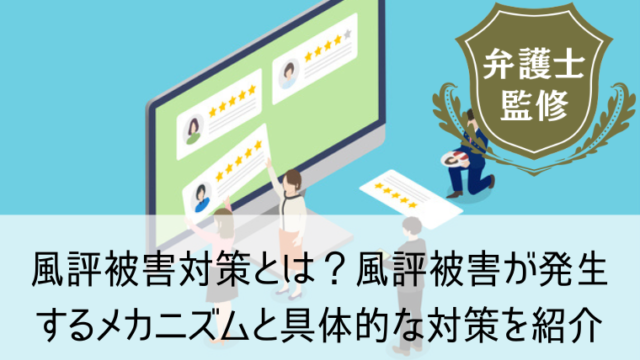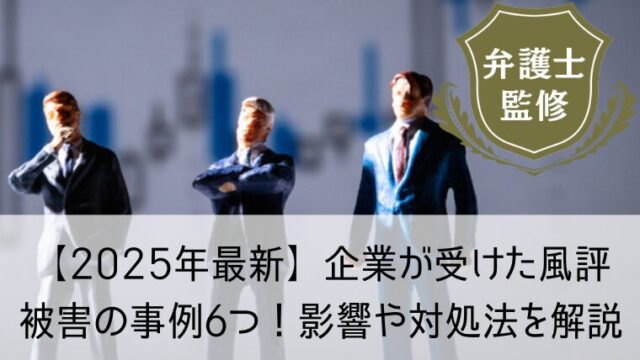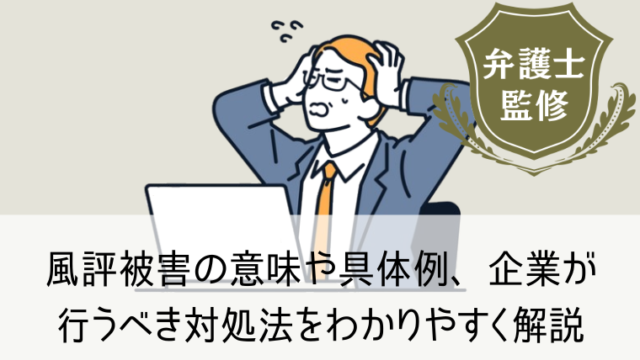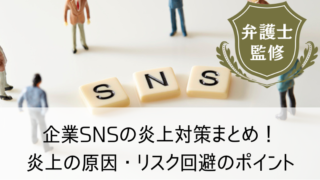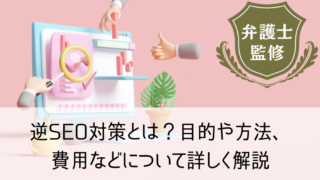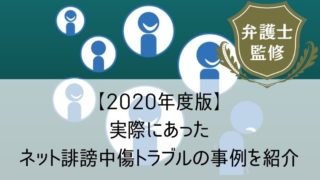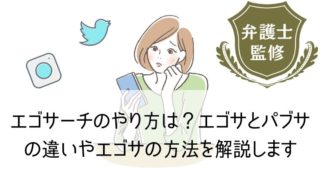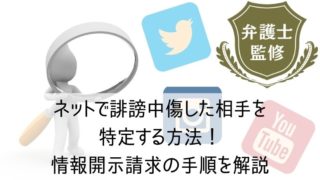インターネット上に広がる根拠のない噂や誹謗中傷は、企業や個人の信用を大きく傷つける恐れがあります。放置するとGoogle検索結果に表示されたり、掲示板や口コミサイト、SNSで拡散され、深刻な風評被害へと発展しかねません。
風評被害を防ぐには、投稿の削除依頼や法的手続きの方法を把握し、適切に対処することが重要です。
この記事では、ネット上の悪質な投稿を削除する方法や風評被害への対処法、対策のポイントについて、分かりやすく解説します。
風評被害の原因投稿を削除する方法3つ
インターネット上の掲示板やSNSの悪質な投稿は、早い段階で対処しなければ、風評被害の原因となり得ます。
まずは、悪質なネット投稿の削除方法について、自分でできる方法から弁護士への依頼まで、3つの方法を紹介します。
①掲示板・サイトに削除依頼
もっとも一般的なのは、問題の投稿が掲載されている掲示板や口コミサイトに直接「削除依頼」をする方法です。
通常、Webサイトには「お問い合わせフォーム」や「管理者へのメールアドレス」が用意されているため、そこから削除依頼を送ることができます。
特別な書類を準備する必要がなく、すぐに実行できるのが大きなメリットです。
弁護士に依頼する場合は費用が発生しますが、自分たちで行う場合は費用もかかりません。
削除依頼をする際は、以下の内容を分かりやすく記載することが大切です。
- 削除してほしい投稿のURL
- 問題としている箇所(内容)
- 削除理由(プライバシー侵害や名誉毀損など)など
ただし、削除するかどうかは最終的にサイト運営者の判断に委ねられるため、必ずしも削除されるとは限りません。
個人でも削除依頼は可能ですが、証拠の保全や法的根拠の整理が必要なケースでは、専門知識を持つ弁護士に任せたほうが、削除が認められる可能性は高まります。
②送信防止措置依頼
直接依頼で削除されない場合は、「送信防止措置依頼」も検討しましょう。
送信防止措置依頼とは、「情報流通プラットフォーム対処法」(正式名称:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)によって定義された手続きで、被害者が投稿の削除を依頼できるものです。
送信防止措置依頼を行うには、以下の内容を記載した依頼書を作成し、サイト運営者に提出しましょう。
- 権利侵害を受けている本人の情報
- 掲載されている場所(URLや掲示板の名称、日付など)
- 掲載されている内容
- 侵害されている権利(プライバシー権など)
- 権利侵害を主張する理由や被害の状況
- 発信者への氏名を開示するかどうか
問い合わせフォームやメール、書面の郵送で行うのが一般的で、被害者本人が自分で行うほか、弁護士に代行を依頼することも可能です。
ただし、送信防止措置依頼をしたからといって、必ずしも該当の投稿が削除されるわけではありません。
削除に応じてもらうには、どのような権利が侵害されたのかを具体的に示す必要があります。
証拠の不備や説明不足があると削除されない可能性も高いため、費用はかかりますが、確実な削除を目指すなら弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
③裁判所への申し立て
送信防止措置依頼でも削除が認められない場合は、裁判所に「仮処分」を申し立てる方法もあります。
裁判所から削除命令が発令されれば、削除に応じてもらえるケースがほとんどで、万が一削除してもらえない場合も強制執行が可能なため、安心感があるでしょう。
具体的な方法としては、削除請求の要件を満たす申立書と、権利侵害の証拠(投稿画面のプリントアウトなど)を裁判所に提出します。
裁判所は審尋(しんじん)と呼ばれる手続きで、サイト運営者側の意見や証拠も確認し、削除命令を出すか否かを判断するのが基本の流れです。
ただし、削除命令が認められた場合、申立人は裁判所が指定する額の担保金(30万円程度)を供託(きょうたく)する必要があります。
これは、申し立ての濫用を防ぎ、正当でない申し立てによって相手方が不利益を受けることを防止するための措置です。
削除がされれば、相手方に損害が発生することは普通はないため、供託したお金は戻ってきますが、戻ってくるには通常2ヶ月ほどかかります。
そのため、時間もコストも必要になりますが、確実に削除させたい場合にはもっとも効果的な方法です。
ネット上の誹謗中傷や悪評を消したい!削除以外の対処法3つ

ネット上の悪質な投稿に対して削除依頼をしても、ただちにそれが認められるとは限りません。
裁判所への仮処分申し立てなど法的手続きは時間がかかり、削除が実行されるまでには数週間から数ヶ月を要する場合もあります。
そのため、風評被害を最小限に抑えるには、削除依頼以外にもいくつかの方法を併用することが効果的です。
ここからは、風評被害対策に効果的な削除以外の対処法を3つ紹介します。
①逆SEO対策
逆SEO対策とは、検索結果でネガティブな投稿が上位に表示されないようにする施策です。
企業名や商品名に「やばい」「まずい」といったキーワードが並ぶと、利用者が不安を抱き、企業やブランドのイメージが低下します。
逆SEO対策は、このような場合に検索エンジンに評価される良質なコンテンツを増やし、ポジティブなサイトを上位に表示させる取り組みです。
その結果、ネガティブサイトが相対的に目立たなくなり、企業やブランドのイメージを守ることにつながります。
逆SEOは、SEOに関する専門知識が必要となるため、検索エンジン対策に強い専門会社へ依頼するのが一般的です。
効果が出るまでには一定の時間がかかりますが、どうしても削除が難しい場合に効果的な手法といえます。
②投稿者に損害賠償請求
悪質な投稿によって明らかな損害が生じた場合は、投稿者に損害賠償を請求することも可能です。投稿者への法的措置は、再発を防ぐ強力な抑止力にもなるでしょう。
ただし、投稿者の氏名・住所が不明な場合は、まず発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定する必要があります。
損害賠償請求では、以下の2点を証明することが重要です。
- 該当する投稿が名誉毀損や業務妨害など違法であること
- 経済的損失や顧客離れなど、実際に被害が発生した証拠
弁護士に依頼することで証拠の整理や手続きがスムーズになります。
③警察に被害を訴える
投稿内容が脅迫や信用毀損、業務妨害など刑事事件に該当する場合は、警察へ相談することで、加害者に刑事責任を問える可能性があります。
警察に相談する際には、問題の投稿画面を印刷した資料やURL、投稿日時、被害状況の記録を持参するとスムーズです。
特に被害が継続している場合や実害が顕著なケースでは、早めに動くことで、証拠が消える前に対応してもらえる可能性が高まります。
風評被害がもたらすリスク
インターネット上に書き込まれた悪意ある投稿は、たとえ小さなものでも放置すると企業や個人に長期的なダメージを与えます。
早期に削除依頼を行わない場合、検索結果に残り続けるため、将来的に顧客や取引先の目に触れる可能性は否めません。
続いては、風評被害が企業にもたらすリスクについて、具体例を交えて紹介します。
業績・売上の低下
ネット上の投稿は拡散力が高く、拡散されるタイミングも予測できません。
1件の書き込みでも、放置するとまとめサイトやSNSで広がり、事実無根の内容が真実として受け取られてしまったり、結果として不買運動や顧客離れが起こり、長期的な売上低下に直結するケースもあります。
例えば、2023年には敷島製パン(Pasco)が「コオロギパン」を販売した際、コオロギを食材に使うことへの不安がSNSで急速に拡散し、一部消費者が商品を敬遠する動きが報じられました。
企業側は迅速に反応し、公式WebウェブサイトやSNSを通じて衛生管理や安全性にも万全を期していることを説明しましたが、消費者の嫌悪感を払拭するには至らず、不買運動に発展する事態となっています。
人材流出・採用の難航
ネガティブな書き込みは、既存社員の士気を下げるだけでなく、新たな人材の獲得も難しくします。
求職者の多くはインターネットで企業名を検索するため、検索結果に「ブラック企業」や「パワハラ」といった言葉が並んでしまうと、応募をためらうケースも少なくありません。
株式会社エフェクチュアルが実施した調査では、内定辞退者の約20%が「ネット上のネガティブ情報を見て辞退した経験がある」と回答しており、オンラインの評判が採用活動に直結することが裏付けられています。
中小企業を対象とした別の調査では、約7割の採用担当者が「ネガティブな口コミが原因で応募者が減った」と感じていると報告されており、風評が人材確保に与える影響は非常に大きいといえます。
取引先・金融機関との関係の悪化
風評被害は顧客だけでなく、取引先や金融機関との信頼関係を悪化させる場合があります。
検索結果やSNSに根拠のない悪評が残れば、信用リスクがあると判断され、取引先が契約更新を見送ったり、新規発注を控えたりする可能性もゼロではありません。
金融機関が融資や借り換えに慎重になるケースもあり、資金繰りに直接影響する恐れがあります。
実際に、2023年のビッグモーター問題では、不正報道が広まったことで信販大手ジャックスが自動車ローンの新規受付を停止し、銀行団も借り換え要請への対応を厳格化しました。
不祥事そのものが発端ではあるものの、インターネットでの急速な拡散と世論の高まりが取引先や金融機関の判断を早めた典型的な事例といえます。
風評被害対策のポイント

風評被害を防ぐには、被害の定義を正しく理解し、初期対応を迅速かつ的確に行うことが重要です。
突然のトラブルに備えるためにも、風評被害対策のポイントを押さえておきましょう。
風評被害の定義
風評被害とは、「根拠のない悪口や不正確な情報により、企業や個人が社会的・経済的な損失を受けること」を指します。
刑法上の名誉毀損や信用毀損とは別のものとして定義されていますが、風評を広めた加害者が名誉毀損罪(刑法230条1項)や信用毀損罪(233条前段)に問われるケースもあります。
被害が発生した場合は、まず投稿のスクリーンショットやPDFで、URLを含む形で証拠を保全し、民事の損害賠償請求を行うか、刑事責任を問うかを検討します。
判断が難しいときは、一般社団法人セーファーインターネット協会が設置する「誹謗中傷相談ホットライン」などの窓口に相談するのも良いでしょう。
法的措置に踏み切る際には、投稿削除や発信者情報開示の手順についても専門家からアドバイスを受けるとスムーズです。
重要なのは初期対応
風評被害を拡大させないためには、初期対応を適切に行うことが非常に重要です。
特にX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは情報が想像以上のスピードで広がるため、被害を最小限に抑えるためには早期対応が求められます。
まずは、どの程度拡散しているか、どのような影響が出ているかを把握し、事実関係を確認したうえで公式声明を発信しましょう。顧客や取引先、株主などのステークホルダーに対してきちんと説明を行うことが、信頼の維持につながります。
削除依頼や逆SEO対策など、具体的な施策も並行して進めることが大切です。
風評被害の投稿は「削除依頼」や「逆SEO対策」で適切に対処しよう

インターネット上で悪質な投稿が拡散されると、企業や個人の信用は短期間で失われ、売上や取引先との関係にまで影響する恐れがあります。
被害が小さいからと放置してしまうと、検索結果に残り続け、後から削除しようとすると時間も費用も余分にかかるケースが多いです。
そのため、現時点での被害が限定的であっても、該当する投稿の削除や逆SEO対策など、風評被害を拡大させないための施策を講じることが重要です。
自社だけでの対応が難しい部分につきましては、エルプランニングの「風評被害対策サービス」の導入をぜひご検討ください。
15年間で50,000件以上の対応実績を誇る当社が、企業の風評被害をスピーディーに解決するお手伝いをさせていただきます。
風評調査および専門コンサルタントへの相談は無料です。
ネット上の風評被害についてお悩みの企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。