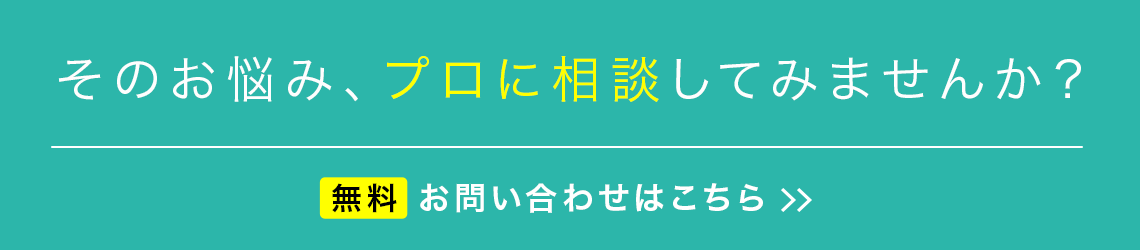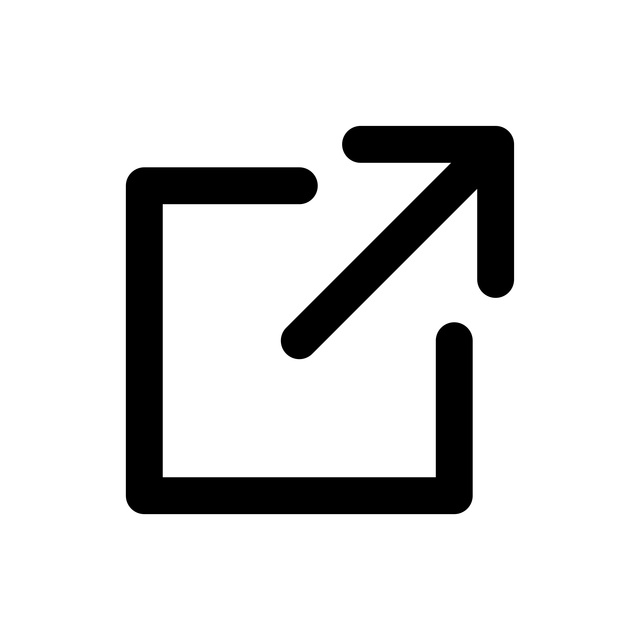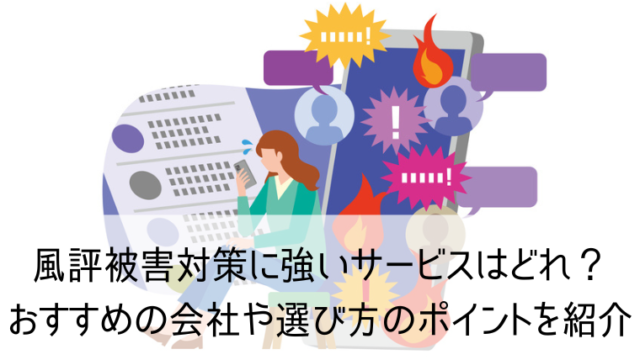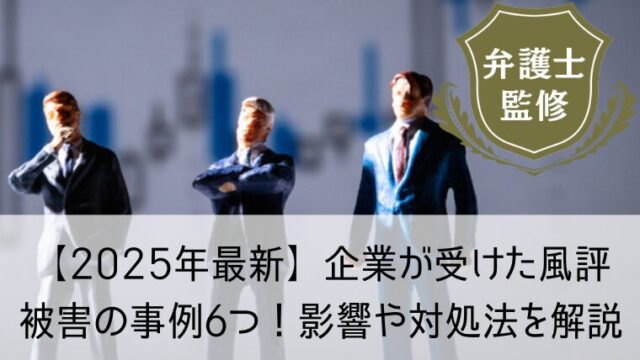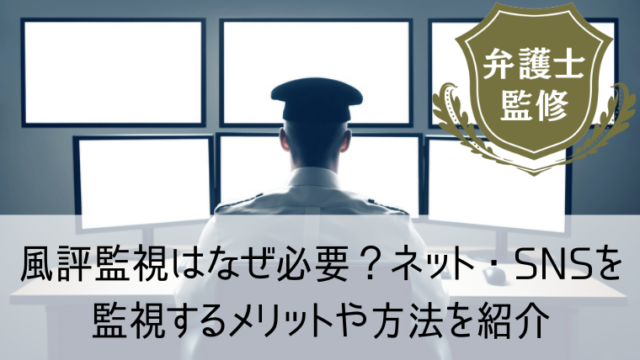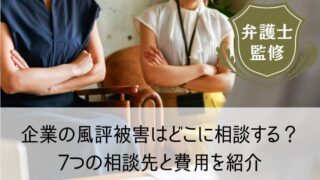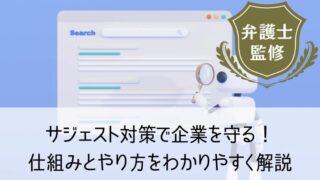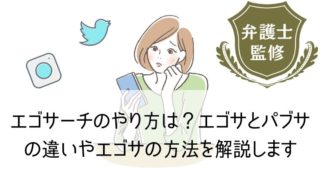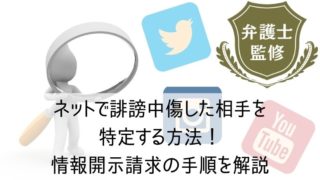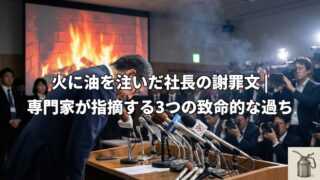インターネットやSNSの普及により、個人だけではなく、企業が思いもよらぬ「ネット風評被害」に巻き込まれるケースが増えています。
事実とは異なる情報や誤解に基づく投稿が拡散され、信用の失墜や売上の減少など、深刻なダメージを受けるケースも少なくありません。
この記事では、ネット風評被害の主な種類や発生の原因、想定されるリスクや、効果的な対策方法について詳しく解説します。
ネット風評被害とは?
ネット風評被害とは、インターネット上に書き込まれた虚偽の情報や誹謗中傷などによって、企業や個人の信用・評判が損なわれることを指します。
具体的には、掲示板やSNS、レビューサイト、口コミ投稿などを通じて、悪意ある書き込みや誤解に基づく情報が一気に拡散されてしまうケースが多いです。
従来の風評被害とは異なり、ネット風評被害には以下のような特徴があります。
- 拡散スピードが圧倒的に速い
- 匿名性が高く、投稿者の特定が困難
- 検索エンジンにネガティブ情報が長期間残りやすい
また、これに加えて近時は「アテンション・エコノミー」の広がりにより、偽・誤情報が拡散されやすくなっています。アテンション・エコノミーとは、情報過多の中で支払える時間が希少となるため、アテンション(関心)が価値を持つようになることを指す言葉です。
より多くのアテンションを集めてクリックされるために、プラットフォーム上では過激なタイトルや内容、憶測だけで作成された事実に基づかない記事等が生み出されることにつながります。
一度拡散されたネガティブな情報は、たとえ事実無根であっても企業活動に悪影響を及ぼしかねません。
そのため、ネット上の風評はできる限り監視するなど、対策を徹底して被害の拡大を防ぐことが重要です。
ネット風評被害の種類・原因

私たちが日常的に利用しているさまざまなプラットフォームで発生します。
投稿者が個人でも法人でも、匿名であっても実名であっても、ひとたび拡散されれば企業やブランドの信用を大きく損なう恐れがあります。
ここでは、ネット風評被害が特に発生しやすい代表的な5つの媒体を挙げ、それぞれの原因・特徴を紹介します。
Google・Yahoo!などの検索結果
GoogleやYahooなどの検索エンジンは、多くのユーザーが企業名や商品名を調べる際に最初に接触する情報源であり、第一印象に強く影響を与えます。
- 検索結果の上位に過去の炎上記事や批判的なまとめサイトが表示される
- 「企業名 やばい」「商品名 最悪」などのネガティブなサジェストが出現する
- 自動表示されるネガティブワードによって、実際の内容を読まなくても悪印象を与えてしまう
Googleのサジェスト(関連キーワード)は、ユーザーの検索行動やトレンドに応じて自動生成される仕組みです。
そのため、何らかの事件や不祥事により、企業名が話題になると、「企業名+やばい」「サービス名+炎上」といったネガティブワードでの検索が急増し、それがサジェストとして反映されやすくなります。
例えば、飲食チェーンで異物混入が報道された場合、「店名+異物混入」「店名+衛生管理」などの検索が一気に増え、それが予測変換に表示されます。
報道後に問題が解決したとしても、ネガティブな検索履歴がサジェストに残り続けるケースは珍しくありません。
X(旧Twitter)などのSNS
X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのSNSは、誰もが手軽に情報を発信・拡散できるため、炎上や風評被害の発生源になりやすい媒体です。
- 一つの投稿が短時間で何千、何万と拡散されてしまう
- ユーザーの共感や怒りが集まり、企業や個人に対するバッシングが一気に広がる
- トレンド入りやハッシュタグによって、さらに注目されやすくなる
SNSによる風評被害は、不適切な投稿や広告表現、従業員の言動、企業の対応への不満などがきっかけとなるケースが多く見られます。
誰でも気軽に投稿できるため、悪意のない一言が大きな批判を招くことも珍しくありません。
また、投稿者の誤解や感情的な反応が連鎖的に拡散されることで、企業側に非がなくても誤解を生み、大規模な風評被害につながることがあります。
ブログや掲示板
ネット上にある匿名掲示板や個人ブログは、ユーザーが自由に投稿できる一方で、風評被害が発生するリスクも高い媒体です。
- 憶測や虚偽に基づく投稿が事実のように広まる
- 「内部告発風」の書き込みが企業の信頼を揺るがす
- 過去の記事やコメントが何年にもわたり検索結果に表示され続ける
掲示板やブログでは、企業の内部情報を知る第三者が「関係者」を名乗って批判的に書き込むケースが多く、不確かな情報がそのまま信じられて拡散されることがあります。
事実無根の投稿や、実体験を装った企業批判、内部告発風の投稿が繰り返されると、企業イメージに深刻なダメージを与えかねません。
また、過去に一度投稿された内容が削除されずに残り続けるため、何年も経ってから検索により再燃するリスクもあります。
口コミ・レビューの評価
Googleマップや口コミサイトに寄せられるコメントやレビューから、風評被害が広がるケースもあります。
たとえ少数であっても、悪意ある低評価や虚偽の口コミが並んでいると、第三者からの印象は大きく損なわれてしまうでしょう。
- 少数でも星1レビューが続くと、平均点が大きく下がる
- 実際にサービスを利用していないユーザーからの虚偽投稿
- 競合他社による悪質なレビュー操作
このような風評被害の背景には、感情的な投稿や、匿名性の高さを利用した誹謗中傷、業者による組織的なレビュー操作などがあります。
特に飲食店や美容業、宿泊施設などは、実体験に基づかない評価でも印象が左右されやすく、低評価が続くと「このお店は危ないのかも」と検索ユーザーに先入観を与えてしまいかねません。
また、競合他社による悪質な投稿や、退職者などの内部関係者が書き込むケースもあり、企業が自らの正当性を説明することが難しいという点も問題です。
口コミやレビューは信頼性を持って受け止められることが多いため、企業側にとって深刻なリスクとなるでしょう。
YouTubeなどの動画プラットフォーム
YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームは、ネット風評被害がもっとも深刻になりやすいとされています。
- 商品やサービスを批判するレビュー動画がバズる
- 企業発信の動画が切り取られ、誤った意図で再編集・拡散される
- インフルエンサーによる批判発言が信憑性を持って広まる
動画コンテンツは、静止画や文章よりも視聴者の感情を強く動かすため、少しの誤解や編集の仕方次第で、大きな炎上や風評被害につながる恐れがあります。
動画の一部分だけを切り取るなど、発言の文脈を無視した再編集が行われ、企業の意図とはまったく異なる形で情報が独り歩きすることも珍しくありません。
また、フォロワーの多いインフルエンサーによるネガティブなレビューや発言は、視聴者に強い影響を与えやすく、情報の正誤にかかわらず「信憑性があるもの」として拡散されてしまう傾向にあります。
再生回数やアルゴリズムによってネガティブな動画が長くおすすめ表示されることで、企業イメージの回復は難しくなっていくでしょう。
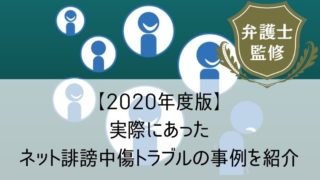
ネット風評被害のリスク
続いては、ネット風評被害によって生じる企業のリスクをまとめていきます。
ブランドイメージの低下
ネット上で悪評や誤解に基づく批判が拡散されると、商品・サービスはもちろん、企業自体のイメージが大きく損なわれてしまいます。
ブランドは長年かけて築いてきた信頼の象徴であり、イメージの回復には多大な時間と費用がかかるでしょう。
例えば、ある飲食チェーンでは、店舗での異物混入がSNSで拡散されたことで、安心・安全というブランドメッセージに対する信頼が一時的に損なわれ、売上が急減した事例があります。
企業の初動対応が遅れたため、隠蔽体質だという批判が広がり、ネット上で風評被害として拡大しています。
売上や顧客数の減少
SNSやGoogleマップなどに投稿された低評価の口コミは、消費者の購買意欲を著しく低下させます。
実際に、悪い口コミやレビューを見たことで、その商品やサービスを避ける消費者は少なくありません。
特にECサイトや予約サイトを利用している業種では、口コミが売上に大きく影響するため、悪意ある投稿が数件あるだけで予約キャンセルや顧客流出が起きるリスクもあります。
既存顧客の離脱が懸念されるだけでなく、新規顧客の獲得も難しくなるなど、売上への影響が直接的に表れやすいです。
採用活動への悪影響
企業の風評は求職者にとって重要な判断材料です。
企業の評判が悪化すると、求職者が応募を控える、内定辞退が相次ぐなど、採用活動に深刻な影響が出ることもあります。
多くの求職者は、ネット上の口コミや評判を重要な判断材料としているため、検索結果やサジェストに「企業名 ブラック」「企業名 パワハラ」などのネガティブワードが表示されると、敬遠される可能性が高いです。
学生向けの就職情報サイトやSNSでの投稿が原因で、インターンや会社説明会の参加者が激減することもあります。
取引先からの信頼喪失
ネット上での悪評が取引先や株主、金融機関の耳に入ると、信頼関係に亀裂が生じることがあります。
信用を重視する業界では、「あの企業と関わるのはリスクがある」と判断され、契約解除や融資の見直しを申し出られる事態も考えられるでしょう。
特に中小企業では、少数の主要取引先に依存しているケースも多く、一社との関係悪化が経営全体に波及する恐れもあります。
社内の士気・モラル低下
外部からの批判や悪評が続くと、従業員の士気にも影響が及びます。
「自分たちの努力が報われない」「この会社に将来はない」と感じる社員が増え、仕事へのモチベーションが低下してしまうでしょう。
外部の風評に敏感になった社員が社内で過度に萎縮したり、社外の声に振り回されてしまうと、優秀な人材が転職を検討するきっかけにもなりかねません。
ネガティブ情報の固定化
ネット上に一度公開された情報は、たとえ事実に反するものであっても、検索結果に長期間表示され続けます。
検索エンジンや口コミサイトに悪評が出続けると、ネガティブ情報が固定化し、新しい顧客や取引先、求職者に対して悪い第一印象を与え続けてしまうでしょう。
削除依頼や風評対策を講じるなど、迅速な対応が必要です。
ネット風評被害の対策方法
ネット風評被害は、企業や個人の評判を大きく損なうだけでなく、売上や採用、取引関係にも深刻な影響を及ぼします。
一度拡散されてしまうと取り消すのが難しいため、早期発見と迅速な対応がカギを握るでしょう。
ここからは、ネット風評被害を最小限に抑えるための対策を具体的に紹介します。
ネット監視(モニタリング)
ネガティブな投稿の早期発見と初動対応のスピードは、ネット風評被害の拡大を防ぐうえで、もっとも重要な要素です。
Google検索結果やSNS、掲示板、口コミサイトなどを定期的に監視し、自社やブランドに関する投稿を早期に察知する体制を整えましょう。
特にSNSは、1つの投稿が瞬く間に拡散される可能性があるため、リアルタイムでの監視が望ましいです。
モニタリングには、社内での手動チェックだけでなく、AIを活用した自動監視ツールの導入や、外部の専門業者への委託も検討しましょう。
エルプランニングでは、自動ツールと有人確認を併用した高精度の「ネット監視サービス」を提供しています。
SNSの投稿や掲示板上のキーワードを継続的に追跡し、炎上リスクのある投稿や拡散の兆候をリアルタイムで通知します。
報告書のカスタマイズや対応アドバイスも含まれた包括的なサポート体制が整っています。
監視範囲や報告内容はカスタマイズが可能で、万が一炎上が発生した場合のフォローも充実しておりますので、ぜひご活用ください。
サジェスト・検索結果の対策
企業名や商品名で検索した際に、「ブラック」「クレーム」「倒産」などのネガティブな関連ワードが表示されると、企業の第一印象に悪影響を与えます。
また、検索結果の上位に批判的な記事や掲示板の投稿が表示されることも、信頼低下の要因となるでしょう。
このような事態を防ぐには、以下のような対策が有効です。
- 公式サイトやポジティブなコンテンツの作成・強化
- 被リンクの獲得による検索順位の調整
- 検索エンジンへの削除申請
- 逆SEOによるネガティブサイトの順位押し下げ
サジェスト対策と逆SEOを並行して実施することで、より高い効果が期待できます。
エルプランニングでは、GoogleやYahoo!、Bingといった主要検索エンジンに対応し、「サジェスト対策」や「逆SEO対策」を実施しています。
Webマーケティングで培った独自のノウハウを活かし、多角的な視点で対策が可能です。
社員への情報リテラシー教育
風評被害は、外部の投稿だけでなく、従業員による不用意なSNS投稿や情報漏洩から発生するケースもあります。
そのため、社員を対象にSNS利用ルールや情報リテラシーの教育を行い、リスクへの理解を深めることが大切です。
トラブルを未然に防ぐために、定期的な研修やマニュアルの整備も行いましょう。
エルプランニングの「SNSリスクリテラシー研修」では、業種や課題に応じたオーダーメイド型プログラムを提供しています。
民間企業・官公庁・学校法人などで多数の実施実績があり、実施後の満足度は98%以上です。
「新たな学びや気づきがあった」との声も多く寄せられています。
ブランド力の強化と信頼回復
ネット風評被害には、投稿の削除依頼などの防御的な対応だけでなく、ポジティブな情報発信による「攻めの対策」も必要です。
プレスリリースの配信やSNS運用、自社メディアでの継続的な発信を通じて、企業の信頼性や社会的価値を積極的に高めていけば、風評に左右されにくい強固なブランド力を構築できるでしょう。
エルプランニングでは、「SEO対策」や「MEO対策」のノウハウを活用し、企業や店舗の発信力を強化するサービスを提供しております。
特にMEO対策では、飲食店・クリニック・美容室など幅広い業種で2,000件以上の導入実績と80%以上の成果率を誇ります。
風評被害対策と組み合わせてご依頼いただくことで、守りと攻めを組み合わせた戦略的な対応が可能です。
ネット風評被害は早期の対策が重要!エルプランニングにご相談ください

ネット風評被害は、企業経営に大きな影響を与える重大なリスクです。
被害が発生してからの対応だけでなく、発生前からの備えと継続的な情報発信が、企業のブランド力を守るカギとなります。
エルプランニングでは、ネット監視から逆SEO・サジェスト対策、リテラシー研修やSEO・MEO支援に至るまで、風評被害への総合的な対策をワンストップでご提供しています。
専門コンサルタントが、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。