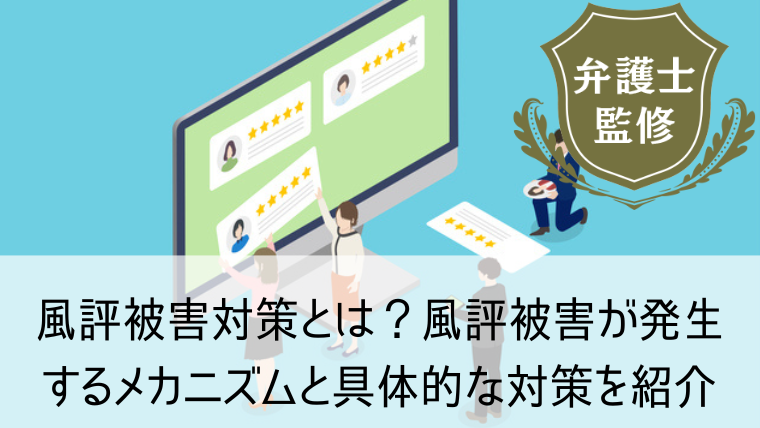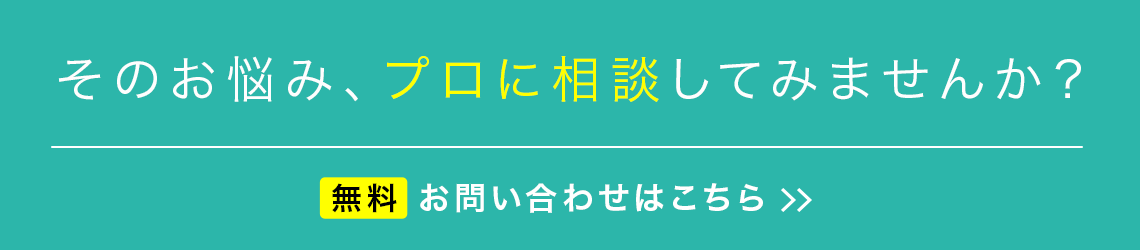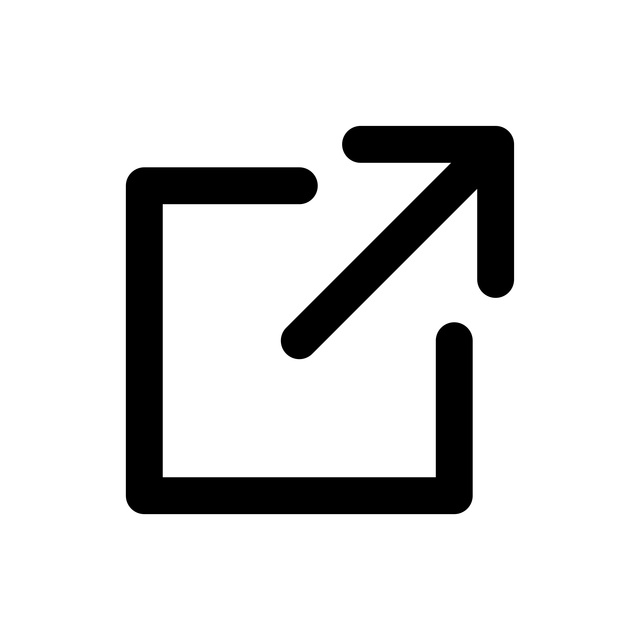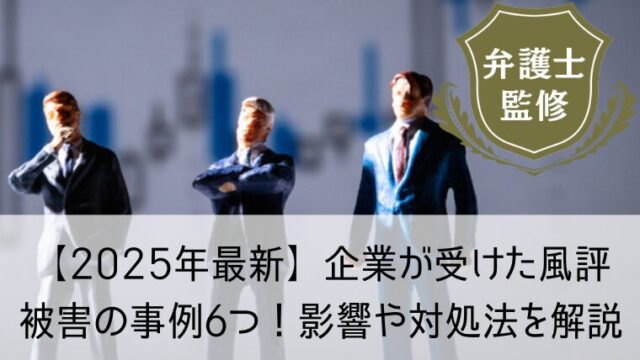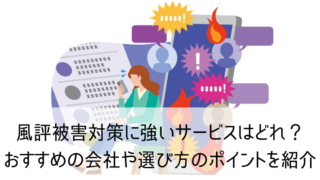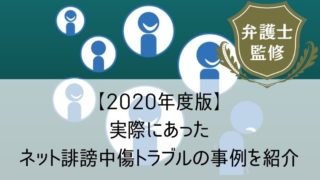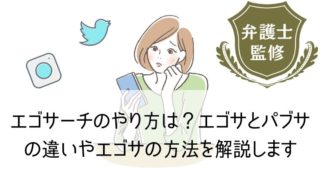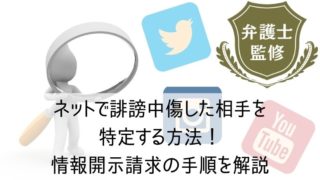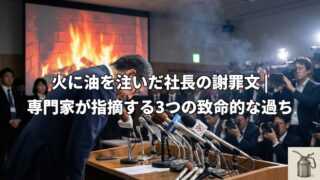SNSや口コミサイトが当たり前になった昨今、根拠のない噂や誤解が一気に拡散すると、企業に大きなダメージを与えることがあります。
企業にとって風評被害は、突然降りかかるリスクであり、いざ発生してから対応するのでは手遅れになるケースも少なくありません。
被害を最小限に抑え、自社を守るためには、風評被害対策を徹底することが重要です。
この記事では、風評被害対策について、企業が今すぐ始められる具体的な方法を分かりやすく紹介します。
風評被害対策とは
風評被害対策とは、インターネットやSNS上で広まる根拠のない悪評や誤情報から、企業や個人の信用・評判を守るための取り組みです。
具体的には、情報の監視、早期対応、社内教育、正確な情報発信、必要に応じた法的措置などを通じて、被害の拡大を防ぎ、信頼回復を図ります。
企業は、風評被害が発生してから対応するのではなく、日頃からリスクを想定した対策を整えておくことが重要です。
正しい情報発信の仕組みを作り、誤情報に対して迅速かつ的確に反応する「予防的な風評被害対策」が強く求められています。

風評被害が発生するメカニズム
SNSや口コミ、ネット記事などを目にした消費者や求職者が、漠然とした不安や不信感を抱くところから風評被害は始まります。
風評被害の原因は、主に以下の通りです。
- SNSでの不適切な投稿
- 根拠のない噂やデマ
- ニュース報道の誤解や誇張
- 消費者の口コミやレビューの誤情報
- 意図的な情報操作
また、風評被害は次のような流れで拡大していきます。
ステップ1:消費者や求職者が不安を感じ始める
ステップ2:企業の取引先や顧客が反応する
ステップ3:専門家やメディアが取り上げ、注目される
ステップ4:情報拡散が加速され、社会的評価が定着する
企業への不安や不信感が生まれると、取引先や顧客にも波及し、契約の見送りや購買の控えといった行動につながる場合があります。
一部の専門家やメディア、SNSやニュースサイトが問題を取り上げてしまうと、注目度が増し、ネガティブな情報さらに拡散されていくでしょう。
結果として企業イメージが低下し、売上減少や社会的信用を失うなど、企業経営に深刻なダメージを与えるのが、風評被害のメカニズムです。
実際に起きた風評被害の事例
続いては、実際に起きた企業の風評被害について、発生した原因別に例を挙げて紹介します。
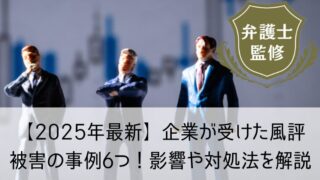
デマによる風評被害
2025年5月頃、「7月に日本で大地震が起きる」という根拠のない予言が香港のSNSで広まりました。
日本への旅行を予定していた人たちの間に不安が広がり、5月後半から航空券やホテルの予約キャンセルが相次ぐなど、経済的なダメージを余儀なくされています。
この状況を受け、航空会社のグレーターベイ航空は徳島と香港を結ぶ便を9月以降すべて運休にすると発表し、仙台〜香港の定期便を運航する香港航空も、10月まで運休する方針を決定することになりました。
これは、単なる噂が現実の行動に大きな影響を与えた風評被害の事例であり、一部の報道では、その経済損失が5,600億円にものぼると試算されています。
誤解から生じた風評被害
2025年2月、牛丼チェーンの松屋が公式X(旧Twitter)に、河野太郎デジタル大臣と駐日ジョージア大使の来店写真を投稿しました。
この投稿の本来の目的は、「シュクメルリ鍋定食」というジョージアの郷土料理をアレンジした限定メニューのPRです。
しかし、一部のユーザーがこれを「政治的なアピール」と誤解し、SNS上では「政治色が強い企業」という批判が一気に広がりました。
実際には有名人が来店した事実を紹介しただけの投稿ですが、ネガティブなイメージが先行することで、風評被害につながってしまった典型的な事例です。
品質低下による風評被害
2024年11月、Xに「チロルチョコに虫が混入していた」とする動画が投稿されました。
包装を開けると中で虫が動いているように見える内容で、インパクトが強かったことから瞬く間に拡散され、「危ないのでは?」と多くの消費者が不安を抱くことになりました。
一方で、チロルチョコはすぐに事実確認を行い、その結果を適切に公表しため、被害を最小限に抑えることに成功しています。
真偽の検証よりも先に悪いイメージが拡散されることで、ブランドや企業全体の信用に影響を及ぼしかねない風評被害の事例です。
不正・不祥事による風評被害
2025年1月、フリマアプリのメルカリで、政府が生活支援として配布した備蓄米が多数出品されていることが発覚しました。
袋には「○○市配布」などの印字が残っており、不正に転売されていることが一目でわかったため大きな批判を呼び、SNSでは「令和の米騒動」というハッシュタグがトレンド入りしています。
問題は出品者の不正行為でしたが、利用者が大量に出品していたことで「企業として監視できていないのでは」とメルカリ自体への批判が集中しました。
結果として、企業の姿勢や信頼性そのものが問われることとなり、これも風評被害の一つの事例です。
風評被害が発生した場合の対応方法

迅速かつ適切な対応が求められるため、事前に具体的な手順を定めておくことが重要です。
ここでは、被害発生時に取るべき具体的な対応について解説します。
事実確認と証拠保存
風評被害が発生した場合、最初に行うべきは事実確認と証拠の保存です。
問題となる投稿や記事の内容を確認し、それが真実に基づいているのか、あるいは誤解や虚偽に基づくものなのかを判断します。
その際、投稿を保存することがとても重要です。
これにより、投稿内容が削除された場合でも、証拠として利用することが可能です。
問題の投稿やコメントが削除されてしまう前に、以下の手順で証拠を確保しましょう。
【証拠保存の手順とポイント】
- PDF印刷
投稿されている個別投稿を表示し、フッターにURLを表示する設定にした上でPDFとして印刷します。まとめサイトなどでは、広告等で問題部分が隠れてしまうこともあるため、適切に印刷されているかの確認をすることが重要です。 - 第三者サービスの活用
ウェブ魚拓などのサービスを使用して投稿の証拠を確保します。 - スクリーンショットの保存
上記の利用が難しい場合は、取り急ぎスクリーンショットでもないよりマシであるため、投稿画面全体が写るように撮影し、投稿日時がわかる形で保存します。その際、該当投稿の正確なURLもどのスクリーンショットのものか分かるように保存します。
保存した証拠は、弁護士への相談時や裁判所への提出資料として非常に重要となるものです。
また、Googleなどの検索エンジンやSNS運営会社への削除依頼の際にも具体的な証拠が求められるでしょう。
法律手続きまでは考えていなくても、企業を守る対策として、できるだけ早く保存しておくことをおすすめします。
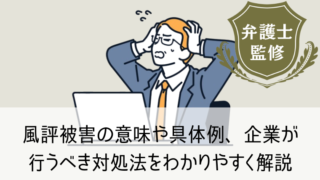
迅速な声明発表と誠実な対応
風評被害に対しては、迅速かつ誠実な対応が求められます。
問題が発生した際、企業としての立場を明確にし、迅速に声明を発表することで、顧客や関係者の信頼を守ることが可能です。
声明内容は簡潔で正確な情報に基づき、問題に対する責任の所在や再発防止策について言及することが望ましいでしょう。
特に、誤解やデマが原因で風評被害が発生した場合には、根拠を持って正確な事実を伝えることが最優先となります。
一方で、企業側に非がある場合には、問題を認めたうえで謝罪し、改善のための具体的な取り組みを提示することが求められます。
誠実な対応を示すことが、企業の信頼回復を早めることにつながるのです。
風評被害が企業に与える影響
風評被害は企業に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
- 売上減少
- ブランドイメージの低下
- 採用活動への悪影響
- 取引先との関係悪化
売上の急激な減少は企業の財務状況を直撃し、顧客からの信頼喪失は、長年かけて築き上げてきたブランドイメージを一瞬で崩壊させてしまうでしょう。
従業員のモチベーション低下は、企業内部の生産性にも深刻な影響を与えます。
風評被害の影響は、単に一時的な問題にとどまらず、人材採用への悪影響、株価の下落など、長期的な経営戦略においても深刻なダメージを受けかねません。
一度失われた信頼を回復するには、通常の数倍の労力と時間が必要です。
特に、デジタル時代において、ネガティブな情報は瞬く間に拡散されるため、迅速かつ的確な対応が求められます。
風評被害を未然に防ぐための対策
SNSや口コミサイトでの風評は、ある日突然発生し、予想以上のスピードで拡散していきます。
悪評が拡大してから対応しようとしても、手遅れになるリスクが高いため、企業は平時からの備えが何より重要です。
ここでは、自社で実施できる基本的な風評被害対策を紹介します。
SNS・口コミの常時モニタリング
X(旧Twitter)やInstagram、TikTok、Googleマップのレビュー、Yahoo!知恵袋、5ちゃんねるなど、情報発信の場は多岐にわたります。
自社名や商品名、サービス名に関する投稿を継続的にモニタリングすることで、悪評や誤情報の拡散など、風評の火種をいち早く察知できるでしょう。
異常を察知した際に、誰が、どのように対応するのかというフローをあらかじめマニュアル化しておくことも、風評被害対策の一つです。
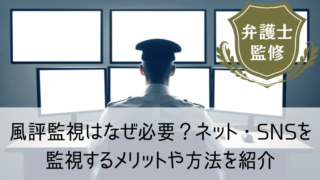
誤情報・悪評への早期対応
SNSやネット記事で誤解を招く情報や明らかな虚偽が見つかった場合、企業は即座に事実確認を行い、適切な情報発信を行う必要があります。
企業の公式SNSやプレスリリース、FAQページなどを活用して、明確な見解や正確な情報を提示することが重要です。
対応が遅れると、「企業が沈黙している=認めている」「何か隠しているのではないか」など、誤った認識を持たれやすくなってしまうでしょう。
スピーディーかつ冷静な対応が、風評被害の拡大を防ぐことにつながります。
社員・関係者のSNS教育
企業の風評被害の原因は、外部からだけでなく、内部関係者の不用意なSNS投稿に起因することもあります。
社員やアルバイトが軽い気持ちで発信した情報が炎上を招き、企業全体の信用を損なうケースも少なくありません。
そのため、従業員に対するSNSリテラシー教育は、風評被害対策として非常に重要です。
社内研修を実施し、個人の発信がもたらす企業への影響を全従業員に周知するとともに、組織全体でリスクを共有しておくことも、風評被害対策につながります。
エルプランニングが提供する「SNSリスクリテラシー研修」は、企業や団体ごとの課題や目的に合わせて内容を柔軟にカスタマイズできるオーダーメイド型の研修サービスです。
SNSの基礎知識や炎上事例の解説に加え、リテラシー向上を目的としたケーススタディや炎上疑似体験ワークショップ、チェックテストなど、実践的な内容が含まれています。
風評被害対策として、風評を未然に防ぐ社内体制を整えたいとお考えの企業様は、ぜひ導入をご検討ください。
企業サイトやプレスリリースの活用
風評が発生した際、自社サイトや公式ブログ、プレスリリースは、自社の主張や事実を正確に伝えるための手段となります。
日頃から、「企業の想いや方針」「取り組み」など、自社の正確な情報をわかりやすく発信しておくことで、誤解や憶測を打ち消す材料となり、万が一の際の信頼回復に役立つでしょう。
また、SEO対策を意識して適切なキーワードで情報を発信しておけば、ネガティブ情報よりも公式情報が上位表示される可能性が高まり、インターネット上のイメージ改善にもつながります。
再発防止策の提示
風評被害が収束した後には、同様の問題が再発しないよう対策を行う必要があります。
まずは、発生原因を詳細に分析し、内部プロセスや体制に問題がないかを見直しましょう。
具体的には、従業員のSNS利用ポリシーを強化したり、商品やサービスの品質管理を徹底したりすることが有効です。
顧客や従業員からのフィードバックを積極的に収集し、それを基に改善を図ることも大切です。取り組みを社内外に示すことで企業の誠実さをアピールし、信頼を取り戻していきましょう。
リスク管理体制の整備
長期的な風評対策の成功には、社内のリスク管理体制を整えることが不可欠です。
リスク管理担当者やチームを設置し、風評被害の兆候を察知した際に迅速に対応できる仕組みを構築しましょう。
外部の専門業者との連携を強化することも効果的です。
専門家の知見を活用することで、リスク管理体制の精度を向上させ、風評リスクに対する迅速かつ的確な対応が可能になります。
風評被害対策サービスの選び方

風評被害に対応するには、自社での取り組みに加えて、専門業者のサポートを活用することが有効です。
ここでは、風評被害対策サービスを選ぶ基準とポイントについて詳しく解説します。
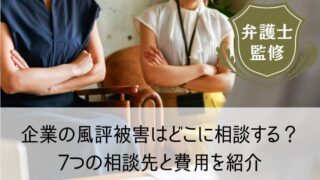
実績と信頼性の確認
まずは、専門業者の実績を確認しましょう。
ホームページやパンフレットを確認し、これまでに対応した案件の数や規模、解決までの具体的なプロセスが明示されていれば、信頼性が高いといえます。
過去の実績や成功事例が豊富な業者であれば、安心して依頼できるでしょう。
業者の信頼性を確認するには、顧客からのレビューや評判を調べることも有効です。
特に、他社の広報担当者や経営者からの評価が高い業者は、実績と信頼性が裏付けられている可能性が高いです。
費用とサービス内容のバランス
費用とサービス内容のバランスを慎重に検討することも大切です。
一見すると高額に見えるサービスでも、問題解決の迅速さやリスク軽減効果を考慮すれば、結果的にコスト効率が良い場合もあります。
ただ安いというだけで飛びつくのではなく、複数の業者に見積もりを確認し、サービスの範囲(モニタリング、削除依頼、法的サポートなど)や内容を比較することが重要です。
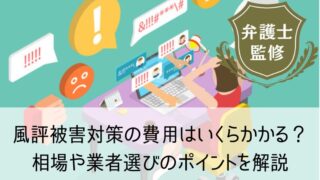
サポート体制と対応スピード
風評被害は時間との戦いです。
そのため、24時間対応可能なカスタマーサポートや、専属の担当者が付くサービスは、特に評価が高いポイントとなります。
さらに、具体的な対応スピードも重要な要素です。
問題発見から初動対応までのスピード感は業者によって異なるため、事前に流れを確認しておきましょう。
対応の遅れが被害の拡大を招くことがあるため、迅速さは選定の決め手となるでしょう。
企業の風評被害対策におすすめのサービス
ここからは、企業の風評被害対策におすすめのサービスを厳選して紹介します。
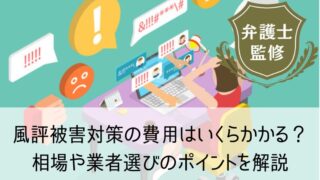
法的対応・削除依頼
SNSや掲示板で誹謗中傷や虚偽の情報が書き込まれた場合、放置することは非常に危険です。
内容によっては、企業の社会的信用を大きく損なうだけでなく、取引先や顧客離れにつながる可能性もあります。
一方で、投稿の削除依頼や法的措置には専門的な知識と対応スキルが求められるため、企業単独での対応には限界があるでしょう。
風評被害につながる投稿の削除申請や訴訟対応は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
逆SEO対策
風評被害の中でも見落とされがちなのが、検索エンジンでのネガティブ情報の上位表示です。
たとえ事実と異なる内容でも、検索結果に悪評が表示され続ければ、ユーザーに与える印象は大きく損なわれてしまいます。
このような事態に対処するのが「逆SEO対策」です。
逆SEO対策とは、信頼性のあるコンテンツを増やし、検索結果の上位にポジティブな情報を表示させることで、悪評を下位に押し下げるという風評被害対策の手法です。

エルプランニングでは、「ブランドSEO」という独自手法を活用し、企業名や製品名などの関連キーワードで検索された際に、ユーザーにポジティブな印象を与えるページが優先的に表示されるよう対策を行います。
企業の信頼やブランドイメージを長く守り続けるために、効果的な取り組みです。
ネット風評被害の即解決ならエルプランニング
サジェスト対策
Googleなどの検索エンジンでは、企業名や商品名を入力した際に表示される「サジェスト」が、ユーザーの印象を大きく左右します。
サジェスト欄に「炎上」「詐欺」「ブラック」などのネガティブワードが表示されてしまうと、企業の信頼性は一気に損なわれ、問い合わせ数や売上の低下につながるリスクがあるでしょう。
風評被害を防ぐには、「サジェスト対策サービス」が有効です。
エルプランニングのサジェスト対策サービスでは、風評リスクとなるネガティブワードを正確に把握したうえで、検索アルゴリズムに沿ってポジティブなワードを自然に表示させる対策を行います。
ユーザーの検索傾向や競合状況を精査しながら、検索サジェストを最適化し、企業イメージの悪化を未然に防ぐのはもちろん、信頼性の高い関連キーワードを誘導的に育てることで、ブランド価値を高め、検索体験そのものを改善する効果も期待できます。
風評被害の芽を早期に摘み取りたい方、検索時の企業イメージを整えたい方は、ぜひサジェスト対策の導入をご検討ください。
専門チームによる監視
風評被害の種となる情報は、SNS、掲示板、レビューサイト、ニュースコメント欄など、あらゆる場所に潜んでいます。
これらを24時間体制で、社内リソースだけで監視し続けることは、現実的ではありません。
エルプランニングの「ネット監視サービス」は、AIによる自動検出に加え、専任スタッフによる目視チェックを組み合わせることで、正確かつ迅速なリスク検知を実現しています。
早期発見により、炎上を未然に防ぐだけでなく、拡大前の風評被害対策が可能になるという大きなメリットがあります。
ブランドイメージの再構築支援
風評被害が一定の広がりを見せた場合、単に被害を食い止めるだけでは信頼回復は困難です。
そのため、「守り」の対策に加えて「攻め」の施策を講じることも重要になるでしょう。
例えば、自社ホームページのデザインや内容を一新する、MEO(地図検索対策)を強化する、ポジティブなプレスリリースを継続的に出すといった取り組みは、企業イメージの再構築に有効です。
エルプランニングでは、状況に応じてブランド戦略・PR活動の立案から実行までトータルで支援しており、企業の本来の価値や魅力を効果的に伝えるための施策を提案します。
「Webサイト制作サービス」から「SEO対策サービス」、「MEO対策サービス」まで、幅広いサービスを組み合わせ、再起を目指す企業の信頼回復と認知向上に向けた総合的な支援が可能です。
風評被害からの脱却を図り、企業イメージを再構築したいとお考えの方は、ぜひエルプランニングにお問い合わせください。
風評被害対策は継続的な取り組みが重要!エルプランニングにご相談ください

インターネット上で事実無根の情報が拡散されると、企業は深刻な風評被害にさらされる恐れがあります。
このようなリスクから自社を守るためには、SNS監視や社内教育、正確な情報発信といった平時からの風評被害対策が重要です。
自社だけでの対応が難しい部分については、エルプランニングの「風評被害対策サービス」の導入をぜひご検討ください。
当社には、15年で50,000件以上の対応実績があり、万が一の事態が発生した際にも、迅速かつ的確な対応で企業ブランドを守ります。
専門コンサルタントが、1社1社に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。