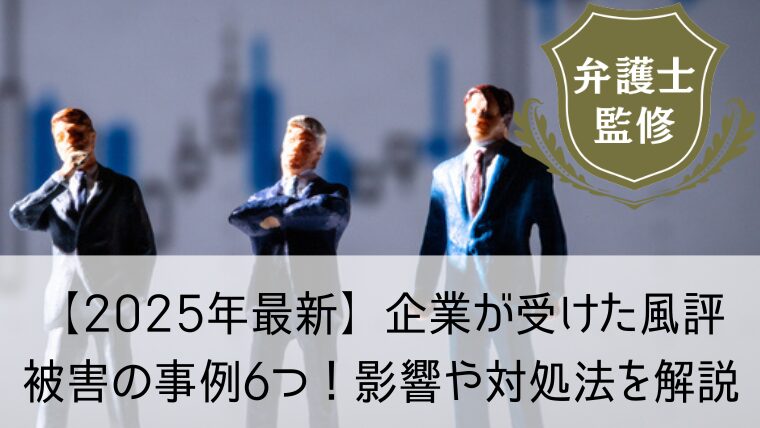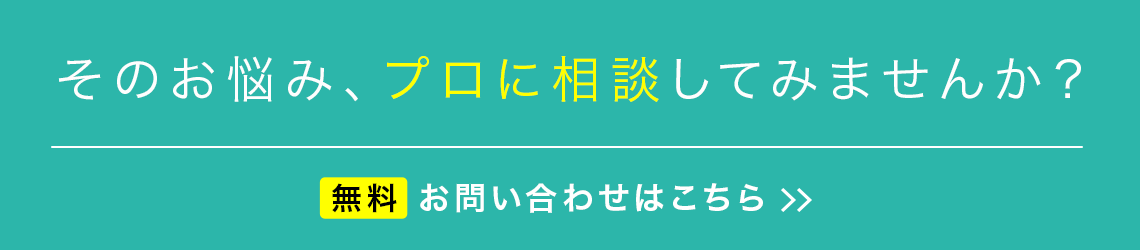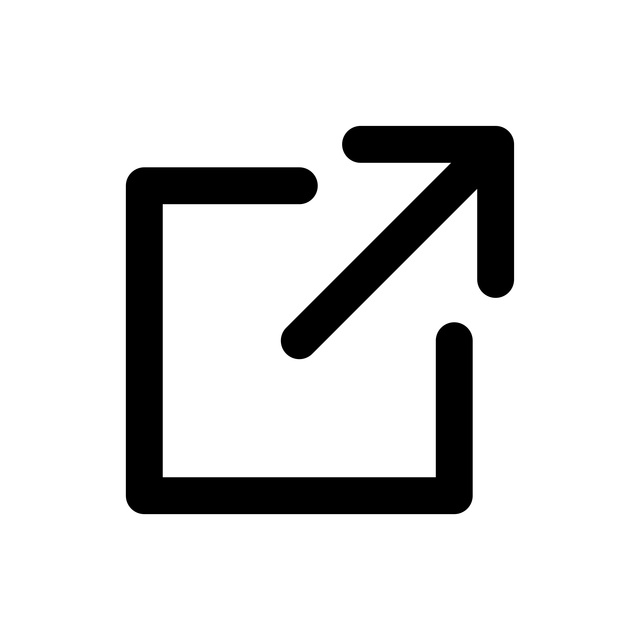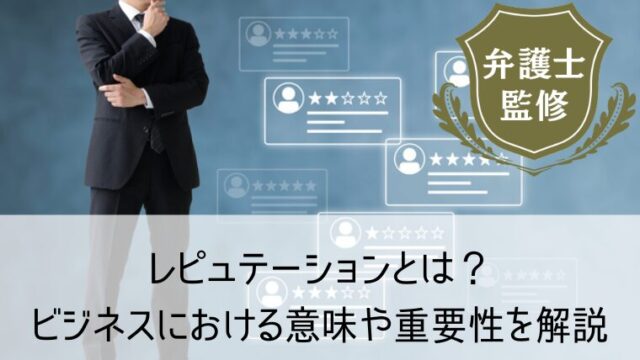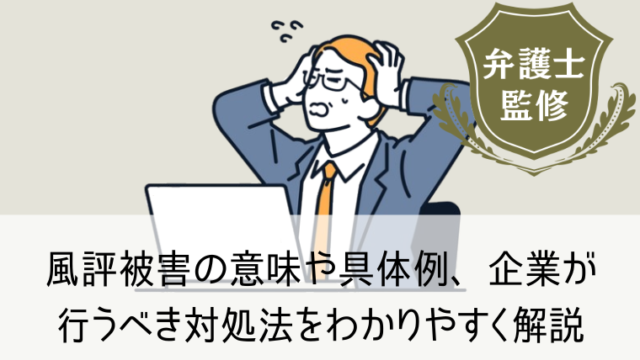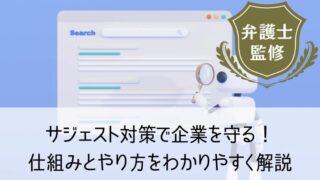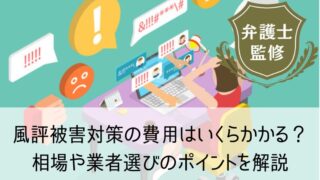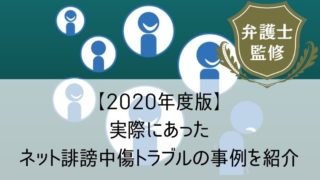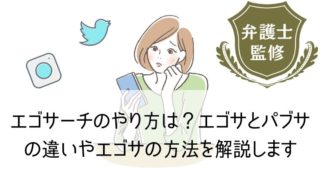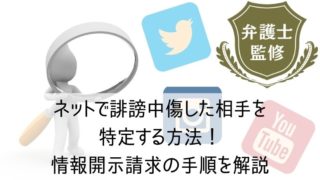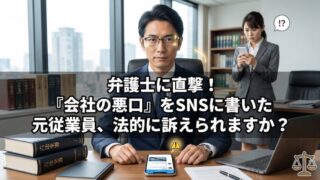SNSや口コミサイトの普及により、企業は予期せぬ風評被害にさらされるリスクが高まっています。根拠のない誤情報や誇張された噂が拡散されると、売上の減少や取引先からの信用喪失など、深刻な経営ダメージを引き起こすこともあります。
この記事では、実際に企業が受けた風評被害の事例を6つ紹介し、その影響や企業の対応、被害の拡大を防ぐための対処法についてわかりやすく解説します。
実際に起きた風評被害の事例

例えば、商品に対する誤情報やキャンペーンでの表現、政治的発言の誤解などが引き金となり、不買運動や採用難、株価下落といった実害へと発展したケースも少なくありません。
ここでは、実際に発生した企業の風評被害事例を紹介し、それぞれの発生原因や企業の対応、その結果について解説します。
1.大地震の予言による航空会社の運休(2025年)
2025年7月、香港の格安航空会社(LCC)グレーターベイ航空は、徳島~香港の定期便を9月から全便運休すると発表しました。
その原因となったのが、香港のSNS上で拡散された「2025年7月に日本で大地震が起きる」という根拠のない予言です。
この予言が香港で大きな話題となり、訪日を予定していた観光客の間に不安が広がった結果、5月後半から渡航を控える動きが加速しました。
仙台〜香港の定期便を週3往復運航する香港航空も、同じく10月まで運休する方針を決定しており、大地震の予言による経済損失は、5600億円程度になるという試算も報じられています。
この事例は、SNS上の噂やデマが、観光や航空運航にまで実害を及ぼす可能性があることを示し、企業や自治体は、適切な情報発信と風評管理の重要性を再認識せざるを得ない事態となりました。
2.松屋の政治家来店投稿への批判(2025年)
2025年2月、牛丼チェーン「松屋」がX(旧Twitter)の公式アカウントで、河野太郎デジタル大臣と駐日ジョージア大使が来店した際の写真を投稿したところ、SNS上で思わぬ批判が巻き起こりました。
この投稿は、松屋が販売していた期間限定メニュー「シュクメルリ鍋定食(ジョージアの郷土料理)」のPRの一環で行われたものであり、政治的な意図はないと考えられます。
しかし、河野氏に対する否定的な感情を持つ一部のユーザーから、「政治色を出す企業は応援できない」「松屋はもう利用しない」といった批判の声が相次いだのです。
SNSや掲示板では「企業の政治的中立性」について議論が広がり、ネットニュースでも取り上げられる事態に発展しました。
一方で、「単に有名人の来店を紹介しただけ」「過剰に反応しすぎでは」といった冷静な意見も多く見られ、「今後も普通に松屋に行く」という声も多数あったようです。
松屋はこの件に対し、投稿の削除や謝罪は行わず、企業としてのスタンスを明確にせず静観を貫く姿勢を取りました。結果として炎上は一過性のもので終わり、商品やブランドへの深刻な影響には至っていません。
この事例は、政治家が関わるSNS投稿が誤解を生む可能性があること、また炎上に対してどう対応するかが企業の信頼性に関わる重要な判断であることを示しています。
3.メルカリにおける米の転売問題(2025年)
2025年1月下旬、フリマアプリ「メルカリ」などで、政府の備蓄米とみられる米袋が大量に出品されていることが発覚し、SNSを中心に大きな話題となりました。
これらの米は、政府が低所得世帯などに対して生活支援の一環として無償配布したもので、明らかに転売目的での出品が行われていたと見られています。
なかには、「○○市配布」などと印字された袋のまま販売されている例もあり、信頼性の高い情報源からも公的支援品の不正利用として懸念が表明されました。
X(旧Twitter)では「令和の米騒動」といったハッシュタグがトレンド入りし、出品者に対する批判だけでなく、メルカリの対応の遅さや監視体制の甘さにも非難の声が集まったのも特徴的です。
最終的に、メルカリは「政府の備蓄米など支援物資の出品を禁止する」と公式に発表し、違反出品の削除と注意喚起を強化しています。
この一連の騒動は、生活支援物資の転売という社会的な問題に加え、プラットフォーム運営者の対応が企業イメージに与える影響を再認識させる出来事となりました。
4.チロルチョコに虫混入疑惑(2024年)
2024年11月、X(旧Twitter)上に「チロルチョコに生きた虫がいた」とする動画が投稿され、消費者の間で不安が急速に広がりました。
動画では、チョコレートの包装を開けると同時に小さな虫が動いているように見え、多くのユーザーがショックを受けた様子をコメントしています。
これを受け、チロルチョコは即日対応に乗り出し、事実確認とともに詳細な調査結果をSNSおよび公式サイトで公開しました。
動画の内容を精査した結果、異物混入の可能性は極めて低いことを説明しつつも、万が一に備えた再発防止策についても丁寧に言及しました。
特筆すべきは、初期の投稿者が企業の調査報告を受け入れ、自発的に謝罪と訂正の投稿を行った点です。
これにより、チロルチョコに対する過度な批判は収束し、企業の誠実な姿勢が広く評価されました。
東洋経済オンラインやスポーツニッポンなどでも、迅速かつ丁寧な対応を「模範的」と報道し、J-CASTニュースでは投稿者とのやり取りまで詳細に紹介されています。
この一件は、誤解に基づく風評被害が拡散しやすいSNS環境下において、企業の迅速で透明性のある対応が信頼回復の鍵となることを強く示す事例となりました。
5.亀田製菓の移民発言を巡る炎上(2024年)
2024年12月、米菓メーカー・亀田製菓のインド出身会長が「日本はさらなる移民の受け入れを進めるべきだ」と発言したと、国際通信社AFPが報道しました。
この内容がSNS上で拡散されたところ、「外国人経営者が日本の将来を勝手に語っている」「米菓は日本文化の象徴であり、日本人の手で守るべきだ」といった批判が殺到したのです。
特に、保守的な立場のユーザーからの反発が強く、一部では不買運動を呼びかける動きも見られました。
また、過去に同社が一部商品で中国産米を使用していたという事実も掘り返され、「外国産志向の企業である」「日本文化を軽視している」といった論調も加わり、企業イメージに対する打撃が懸念される状況となりました。
しかし、実際のインタビュー内容を確認すると、同会長は「多様な人材を活かす社会の重要性」や「グローバル化に適応する必要性」について述べていただけであり、移民政策そのものを直接的に推進する発言ではなかったことがわかっています。
「immigration(移民)」という言葉も使っておらず、一部の報道が文脈を誤って伝えた可能性が指摘されています。
亀田製菓はこの件について、公式ウェブサイト上で明確な釈明や声明を発表していません。しかし、メディアや有識者による事実確認や冷静な解説が相次いだことで、一部のネットユーザーの間では誤解が解け、議論は次第に沈静化しました。
一時的に株価が下落するなどの影響はありましたが、誤報である可能性が周知されるにつれて、不買運動などの過激な反応も徐々に収まりをみせています。
この亀田製菓の炎上は、国際報道の受け止め方やSNS時代における情報拡散のリスクを浮き彫りにした事例といえるでしょう。
6.Pascoの「コオロギパン」騒動(2023年)
2023年、敷島製パン(Pasco)がSDGsや将来の食糧問題への取り組みとして期間限定販売した「コオロギパン」が、SNS上で大きな誤解と混乱を招きました。
この商品は、国連も注目する昆虫食の一環として、コオロギパウダーを使用したパンで、栄養価が高く環境負荷も少ないというメリットがあります。
しかし、発売直後からネット上では「Pascoの全商品にコオロギが混ざっている」「食べたら健康被害が出る」といった事実無根の情報が飛び交い、一部メディアでも不正確な表現で取り上げられたことにより、混乱が加速しました。
このような風評に対し、Pascoは迅速に反応し、公式ウェブサイトやSNSを通じて「コオロギパウダーは特定商品のみ」「他製品とは製造ラインも完全に分けている」と明確に説明し、衛生管理や安全性にも万全を期していることを詳しく発信しました。
日経DIMEやJ-CASTニュースなどのメディアも、企業の対応を後押しする形で、昆虫食の意義やPascoの姿勢について丁寧に報道しています。
正確な情報を広める努力が続けられましたが、消費者の「虫への生理的な嫌悪感」は根強く、誤情報の印象を完全に払拭するには至らず、Pascoはコオロギパンの販売を終了しました。

風評被害を放置するとどうなる?

企業の信頼と安定した経営を守るためには、被害が拡大・定着する前に早期の対応を行うことが重要です。
風評被害を軽視し、対策を取らずに放置してしまうと、企業にとって深刻なダメージを招くおそれがあります。
企業イメージが悪化する
SNSや口コミサイト、検索結果にネガティブな情報が表示され続けることで、企業のイメージは長期間にわたって損なわれます。
特に「○○ 会社名」で検索した際に悪評が上位表示されると、第一印象が大きく悪化します。
一度悪化したイメージを払拭するのは、容易ではありません。
企業イメージの回復には、広報活動やブランディング施策を含めた長期的な対応が必要になります。
業績や経営が悪化する
実際に、SNSで拡散された誤情報が原因で不買運動に発展し、売上が急減した企業も存在します。
風評によって取引先から契約を打ち切られたり、新規の営業活動が困難になるケースもあるため、事実でない情報であっても企業経営に深刻な影響を与えるリスクがあります。
人材確保が難しくなる
企業に関する悪評が広がると、求職者が応募を敬遠し、人材確保が困難になることがあります。
特に、若年層の就職希望者は、企業の評判をネットで確認する傾向が強く、ネガティブな情報が多いと採用活動が停滞してしまいます。
社内でも士気が下がり、離職率が上昇するなど、組織の安定性に悪影響を及ぼすリスクも無視できません。
社会的信用を失う
風評被害は、顧客だけでなく、株主、取引先、金融機関といったステークホルダーの信頼をも揺るがします。
企業としての信用力が低下すると、融資審査で不利になったり、新たな業務提携や商談の機会を逃すなど、ビジネスチャンスの損失につながるリスクがあります。
被害が拡大・固定化する
風評被害は、対応が遅れるほど被害が深刻化しやすくなります。
間違った情報が半永久的にネット上に残ると、「事実」として定着してしまい、第三者による拡散が続くことになるでしょう。
結果として、信頼の回復には多大な時間とコストがかかるため、初期段階で適切な対応を講じることが重要です。
企業が風評被害を受けたときの対処法【5ステップ】

風評被害が発生した際、企業の信用や売上を守るためには、初動の早さと的確な対応が不可欠です。
SNSや掲示板での情報拡散は瞬時に広がるため、対処に迷ったり放置してしまうと、状況がさらに悪化する可能性があります。
ここでは、企業が風評被害を受けた際の対処法として、基本の5ステップを紹介します。
STEP1.状況を正確に把握する
まず最優先で行うべきは、どのような情報が、どの媒体で、どれほどの規模で拡散しているかを把握することです。
X(旧Twitter)、Instagram、Google検索、口コミサイト、掲示板など、媒体ごとに影響力は異なるため、モニタリングにより全体像を可視化しましょう。
被害の初期段階で、冷静に「情報の出所」と「拡散の経路」を掴むことが、誤った対応を防ぐ第一歩です。
STEP 2.事実確認と社内共有
次に行うべきは、風評の中身が事実か否かを正確に精査することです。
仮に事実でないとしても、感情的に否定するのではなく、法務・広報・人事など関係部署と連携しながら、経緯や背景を客観的に整理しましょう。
また、現場の社員が混乱しないよう、社内でも情報共有を徹底し、問い合わせ対応の方針と対応窓口を統一しておくことが信頼の維持につながります。
STEP 3.不適切な投稿への削除依頼
拡散されている情報に名誉毀損、プライバシー侵害、虚偽内容などが含まれる場合、SNSや掲示板の運営者に対し、正式に削除を申し入れることが可能です。
削除依頼には、違反根拠を明確に示す必要があるため、社内対応だけで難しい場合は、ITやネット法務に強い弁護士に相談し、サポートを受けると良いでしょう。
悪質な投稿者には、発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的対応も検討できます。
STEP 4.必要に応じた公式発表や謝罪
風評が誤情報である場合でも、適切なタイミングで説明や見解を発信することが、企業の誠実な姿勢を示す重要な要素です。
仮に自社側に非がある場合には、率直な謝罪と今後の対応策を速やかに示すことで、ステークホルダーの信頼回復につながるでしょう。
逆に対応が遅れると、「逃げている」「誠意がない」といった印象を与え、かえって炎上が長引く結果になりかねません。
STEP 5.ネガティブ情報への対応
風評被害が沈静化した後も、Googleなどの検索結果にネガティブな情報が表示され続けていると、新規顧客や採用希望者の離脱につながるリスクがあります。
問題の沈静化を図るには、検索結果の改善に加え、ポジティブなコンテンツを継続的に発信するなど、「守り」と「攻め」の両面から対策を講じることが大切です。
エルプランニングの風評被害対策サービスでは、ネガティブ記事を検索結果の下位に押し下げる「逆SEO対策」をはじめ、「○○ 企業名 ブラック」など不本意な関連キーワードが表示されないように調整する「サジェスト対策」を実施しています。
加えて、商品・サービスの魅力や実績など、企業の正しい情報を効果的に発信する「SEO対策」や「MEO対策」、さらに、24時間365日体制でネット上の投稿を監視し、異変を即時にキャッチして対応できる「ネット監視サービス」も提供しています。
検索結果全体の印象を改善するとともに、早期発見により「炎上の芽」を摘むことで、企業リスクを最小限に抑える体制の構築が可能です。
風評被害の事例を参考に適切な対処をしよう!
風評被害は、たとえ事実無根であっても、企業の信頼やブランドイメージに深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
SNSや口コミサイトなどを通じてネガティブな情報が一気に拡散すれば、売上の減少、採用活動への支障、取引先からの信用低下といった実害が生じることも珍しくありません。
最近の風評被害の事例を見ても、企業の適切な初動対応によって炎上を最小限に抑えられたケースがある一方で、対応が遅れたことで不信感が拡大した事例もあります。
重要なのは、事実確認と情報の整理を素早く行い、信頼性のある情報発信や法的措置も視野に入れながら、的確な対処を進めることです。
エルプランニングでは、逆SEOやサジェスト対策、ネット監視といった専門的な施策を通じて、企業の風評被害リスクを多角的にサポートしています。まだ被害が起きていない段階でも、予防策を講じておくことで被害の拡大を防ぐことが可能です。
専門チームが最適な対応策をご提案いたしますので、万が一のリスクに備えたい方や、現在進行中の風評被害にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
[Firefoxブラウザをご使用のお客様へ]
Firefoxブラウザでのお問い合わせが送信できない場合があります。お手数ではございますが、別のブラウザを使用して送信いただくかお電話にてお問い合わせください。ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。